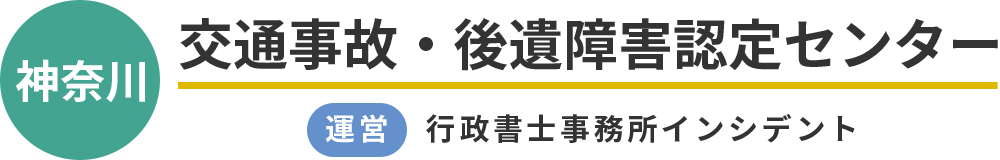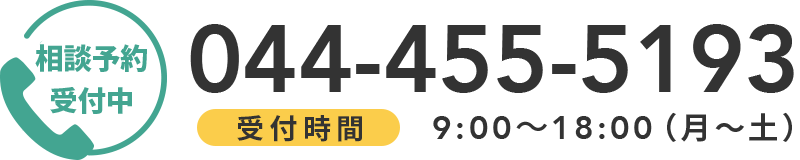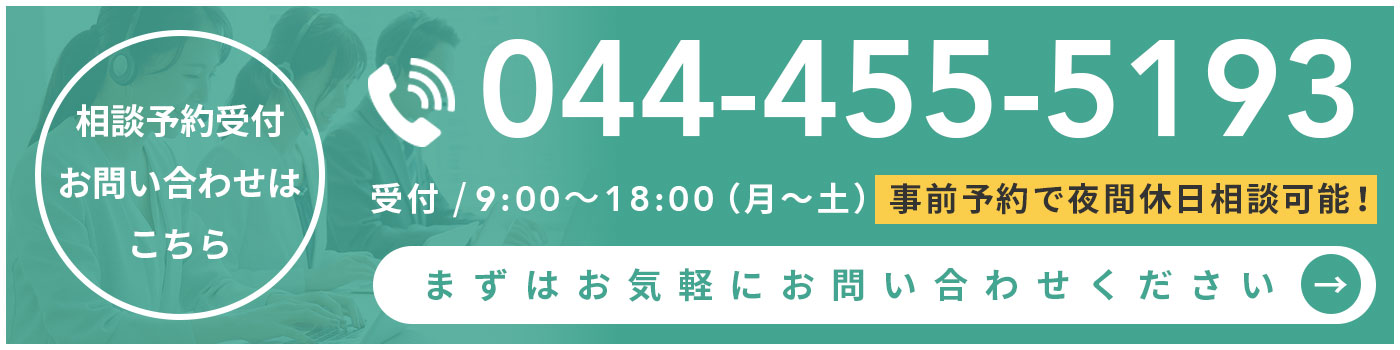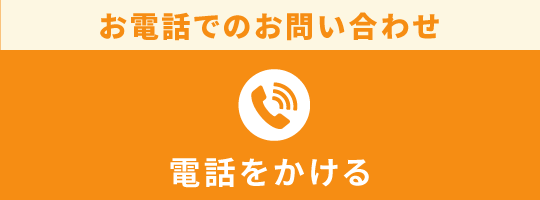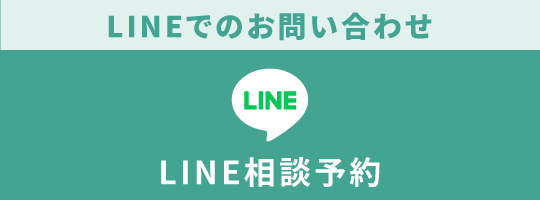Author Archive
交通事故による後遺障害等級審査が長期になる場合
「異議申立」申請は結果まで時間がかかる
異議申立申請の場合、
申請から結果通知まで時間がかかり、
長期に及ぶこともあります。
理由としては、
異議申立申請後は、
医療照会というものがはいります。
この医療照会文書の作成と回答に時間がかかるがために、
結果通知まで時間がかかることがあります。
この医療照会文書の作成時間は、
医療機関にもよりますが、
A.大きな病院に関しては「1ヶ月〜2ヶ月超」の時間を要することもあります。
B.街の整形外科やクリニックは「1〜2週間」で作成をしていただけることが多いです。
初回申請でも結果まで3ヶ月なんてことも・・・
一方、後遺障害等級の初回申請でも審査から結果通知まで、
時間を要することもあります。
最近の事例では、
・初回申請
・医療照会なし
という事案で、申請から約3ヶ月後に、
14級認定の結果通知に至ったケースがあります。
なぜ、ここまで時間がかかったのか、という点については、
具体的な回答がみつかりませんが、
日本の最近の天災事情や新型コロナ禍などから、
保険金の支払いの認証に時間がかかっているのでは?と察します。
僕のお客様も交通事故で困っているものですが、
天災による保険金の支払いを待っているかたもいることを考えると、
自動車保険の支払を先行してほしい、とはなかなか言いにくいものです。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故による頚椎捻挫の他覚的所見
後遺障害等級認定は「まず、画像ありき」
頚椎捻挫後に、首の痛みに加えて、
腕や手に痺れが出ることがあります。
痺れはいわゆる神経症状と考えられ、
主治医先生の指示でMRI画像を撮影し、
その痺れの原因を探ることになりますが、
頚椎部になんら異常がない場合も少なくはありません。
異常所見が見当たらない場合、
”局部に神経症状を残すもの”として、第14級9号の認定を得られれば、
お客様には納得していただく必要があります。
一方、症状を裏付けるMRI画像所見が得られていながら、
自賠責保険上の後遺障害等級審査結果が、
非該当、
ないしは、
第14級9号、
の場合には、
お客様の意向がすべてではありますが、
異議申立申請をすべきケースと考えます。
14級から12級変更認定は可能性がある。ただ、慎重に判断すべき
実際のところ、
腰椎捻挫に関してですが、受傷後の腰部痛、下肢の神経症状が残存しており、
初回申請は14級9号の認定を得たお客様から弊所が異議申立案件として受任しました。
再度、MRI撮影専門機関で、腰部のMRI撮影をしたところ、
症状を裏付ける腰椎椎間板ヘルニアが明らかになりました。
このMRI画像所見を基礎に異議申し立てをしたところ、
(1)受傷当初からの症状の連続性
(2)症状を裏付けるMRI画像所見
という2点を自賠責側に評価いただき、
第12級13号への変更認定を得ました。
このケースは、
(1)異議申立後の医療照会なし
(2)後遺障害等級認定理由に腱反射の評価なし
という稀なケースでした。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
物件事故扱いと自賠責保険上の後遺障害等級の関係
「物件扱い」は14級認定は限界?
まず、交通事故の種別として、
「人身事故」扱いと「物件事故」扱いがあります。
交通事故により怪我をしたのにも関わらず「物件扱い」もあります・・・。
そして、これは弊所のお客様の後遺障害等級認定状況からみた経験ですが、
”物件事故扱い”の場合には、
自賠責保険上の後遺障害等級第14級の認定が”限界”と考えます。
この理由としては、
自賠責保険は、”死亡事故”または”人身事故”の被害者保護が目的である、
というのが、法制度上からの回答かなと考えます。
法制度上からの回答はわかりづらいので、
実際の後遺障害等級認定事案からご案内します。
人身扱いか?物件扱いか?ここが肝
このケースでは、
交通事故により、ご依頼者は腰椎捻挫を(腰椎椎間板ヘルニア)を受傷しました。
事故処理としては、”物件事故”で、
”治療開始から最初の症状固定まで”対応しており、
初回申請で第14級9号の認定を得ました。
その後、異議申し立てを希望し、弊所がご依頼をいただきました。
受任後は、これまでの、
・交通事故証明書
・診断書
・後遺障害診断書
などから事実確認をいたしました。
最初の課題は人身事故に切り替えられるか
弊所でこれまでの事実確認をしたところ、
・症状
・通院の履歴
・これまでの医学的所見
などから第12級の可能性が高いと考えました。
そこで、最初の課題が、
「物件事故から人身事故への切り替え」でした。
事故からだいぶ時間が経過しておりましたが、
お客様をはじめ、
・管轄警察署
・相手方
にもご協力をいただき、
人身事故に切り替えることができました。
弊所の強みである整形外科の紹介
次に、弊所から整形外科をご紹介し転院をしていただき、通院加療を再開していただきました。
この通院と並行して、
MRI専門の医療機関を転院先主治医先生にご紹介いただき、腰椎部のMRI撮影をしていただきました。
MRI結果としては、
腰椎椎間板ヘルニアによる馬尾神経の圧迫所見を得ることができました。
そして、
(1)人身事故扱いへの切り替え
(2)症状を裏付ける腰椎椎間板ヘルニア所見
(3)転院先での後遺障害診断書
を基に、異議申立申請を行いました。
異議申立申請により12級へ変更認定
結果として、
腰椎部について、第12級13号への変更認定に至りました。
実際のところは、物件事故扱いでも第12級認定に至った可能性はあります。
しかし、弊所としては本ケースから、
後遺障害等級第12級以上の可能性が高い案件は、
人身事故にすべきと考えます。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
症状固定後の通院と領収書の保管
症状固定後も通院を継続すること
弊所では、症状固定前からご依頼いただいたお客様には、
”症状固定後の通院の継続”の提案をしています。
理由としては、
異議申立申請による後遺障害等級の変更認定の可能性を残すこと、
が目的です。
弊所で多くお手伝いしております、
頚椎捻挫や腰椎捻挫に限らず、
交通事故による自賠責保険上の後遺障害等級に関して、
初回申請で後遺障害等級が得られるという保証がありません。
最近の自賠責保険の後遺障害等級事情として感じるところは、
初回申請は非該当で回答をしておき、
異議申立申請まで、粘り強く対応をした被害者について、
ようやく適切な後遺障害等級審査をする、認定をする、という流れもあるように感じます。
症状固定後の通院が「新たな医学的所見」にもなる
この異議申立の際、
1.症状固定後の通院
2.症状の連続性を証明
するために、
新たな医学的所見として診断書を添付するのが、
僕が異議申立申請する際の原則です。
※MRI画像や神経学的所見のみが新たな医学的所見となるわけではありません。
症状固定後の通院をした際の領収証も重要
この異議申立申請後に、
領収書の追加提出を、自賠責損害調査事務所(後遺障害審査機関)から求められることがあります。
理由としては、自賠責損害調査事務所側が被害者の、
(1)通院のペースを確認すること
(2)診療内容を確認すること
が主であると考えます。
この領収書の追加提出は、
症状固定前に相手損保会社より治療費を打ち切られ、
健康保険(国保)に切り替えた際にも、
自賠責損害調査事務所から求められることがあるので、
領収書の保管は必須&重要です。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故による腰椎捻挫を受傷した場合の自賠責保険上の後遺障害等級は?
腰椎部で該当する後遺障害等級について
交通事故により腰部を受傷した場合、
腰椎捻挫、
腰部挫傷、
腰椎椎間板ヘルニア、
の診断名がつけられることが多いです。
上記の腰椎捻挫などを受傷した場合に該当し得る自賠責保険上の後遺障害等級は、
(A)局部に”頑固な”神経症状を残すもの:第12級13号
>症状の根拠がMRI画像・腱反射など医学的所見で”証明”できるもの
(B)局部に神経症状を残すもの:第14級9号
>症状の根拠が受傷態様、治療経過などから医学的所見で”説明”できるもの
(C)非該当
と3パターンとなります。
弊所のご依頼者の等級認定の状況
弊所のお客様は、
(B)の局部に神経症状を残すもの第14級9号の認定が多いです。
そして、この第14級9号については、
腰椎捻挫後の腰部痛という”痛み”のみの場合でも、
「局部の神経症状が残存している」として、
認定される可能性はあります。
つまり、腰椎捻挫関連で後遺障害等級認定を得るために、
下肢・足指の”痺れ”の出現は条件ではない、
ということをご理解ください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故でむち打ちなどを受傷し、初回の申請で後遺障害等級併合14級の認定を得ました。
事案の概略
性別・年代:男性(40代)※事故時
事故日:令和3年4月
事故態様:
お客様運転の自転車が道路内を直進していたところ、対向から右折進入してきた相手方自動車に衝突されたものです。
診断名:頚椎捻挫、腰椎捻挫など
症状:
頚椎捻挫由来:頚部痛、左上肢の痺れなど
腰部捻挫由来:腰部痛、左下肢の痺れなど
通院先:
(1)T医療センター
(2)A整形外科
(3)K整骨院
弊所への依頼時期:本件事故から約1週間経過後
争点
(1)相手方損保会社から治療費等の補償を最低でも6ヶ月間受けることができるか。
(2)頚椎捻挫由来の頚部痛などの神経症状を医学的に説明または証明ができるか。
(3)後遺障害等級の認定を得られるか。
事案の内容
1.本件事故のお客様は、事故直後からインターネット検索をし、弊所ホームページをご覧いただいた上で、にご相談&ご依頼をいただいたお客様でした。
初回の面談の際には、痛みで足が曲がらない状態で、身体への衝撃や損傷が大きい事故であったと察しました。
本件事故と初回面談の主なポイントは、
(1)相手損保会社が治療費の支払を3ヶ月程度で打ち切った場合の対策
(2)(1)が具体化した場合、健康保険に切り替えて、週3回程度+3ヶ月超の通院を維持できるかの聴き取り
(3)後遺障害等級認定を勝ち取るための対策
の3点でした。
2.主なポイント(1)(2)について
この点は、本件お客様自身が、自営業者であったということもあり、対外的な調整や交渉に慣れているとのことで大きなトラブルもありませんでした。
結果として、無事に6ヶ月の間、治療費の補償をしていただきました。
本ケースは、率直に申し上げると、症状固定時の実通院日数は”少ない”という結果でした。
当初は、整形外科と整骨院の併用通院をしておりましたが、4ヶ月経過時点で整骨院の治療をやめてしまいました。
この点は、治ったからまたは症状が緩和したからなどの改善をしたことにより治療をやめた、と捉えかねないのでマイナスポイントになると予想しました。
また、整形外科も約6ヶ月の間、週2回のペースであったため、この点も、2022年当時のセオリーでいう「整形外科に週3回」には至っていなかったので、不安要素の一つでした。
自賠責保険請求時のポイント
症状固定の後遺障害診断時には、
(1)症状の詳細
(2)MRI画像所見
(3)神経学的所見
を丁寧に主治医先生に記載いただきました。
本件のお客様の症状として、左上肢・左下肢の痺れ(神経症状)を訴えていたため、
(A)筋萎縮検査:上腕・前腕、大腿・下腿の周径
(B)徒手筋力検査
を主治医先生に実施していただいたところ、その結果が、「左」上肢と下肢の筋萎縮が認められ、そして、筋力低下も認められたため、この点も、左上肢・左下肢の神経症状の裏付けとして、後遺障害診断書に記載していただきました。
初回申請で併合14級認定
自賠責保険上の後遺障害等級認定は、お客様と主治医先生の協力もあり、滞りなく、頚椎部14級9号、腰椎部14級9号の併合14級の認定を自賠責よりいただきました。
後遺障害等級認定のポイントとしては、
(A)お客様の早い判断
>本件は、事故直後からお客様の早いリサーチと判断により、弊所にご相談とご依頼をいただきました。このことによって、
・弊所から整形外科の紹介
・今後の起こりうるリスクのご案内と心構え
など、たくさんの提案や案内ができるので、後遺障害等級の認定の可能性や不測の事態に迅速に対応できたと考えます。
(B)主治医先生の協力を得られたこと
>自賠責保険上の後遺障害等級は、主治医先生の協力を得ることがとても重要です。
この2点と考えます。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
むちうち後の痺れの出現の部位
むちうち後の手の痺れの場所のそれぞれ
むちうち受傷後に、
腕や手に痺れが出現することがあります。
これは、神経学的に、
頚椎から上肢(腕・手)に神経がつながっているためで、
頚椎の損傷部位によって、
痺れの部位に違いがあります。
具体的には、
頚椎C5=腕の内側
頚椎C6=親指・人差し指
頚椎C7=人差し指・中指
頚椎C8=薬指・小指
となります。
痺れの部位とMRI画像所見が一致しないこともある
ただし、現実的には、
痺れの部位と頚椎ヘルニア部位に、
整合性がとれない場合があります。
具体的には、
「右手」の痺れが出現しているのに、
頚椎MRI画像では「正中型」の椎間板膨隆やヘルニアが認められる、
といったケースも少なからずあります。
(※正中型は、「真ん中」のヘルニアという意味で、両上肢や両手に症状が出現するのが典型です。)
このようなケースでも、
後遺障害診断書の記載の仕方などで、
14級認定の可能性は十分にありますし、
実際に認定された弊所のご依頼者もいらっしゃいます。
弊所のアイデアや医師への提案力にお任せください
したがって、手の痺れの部位と頚椎MRI検査結果に整合性がとれなくても、
一喜一憂する必要はないと考えます。
弊所では、各精密検査結果を、後遺障害診断時に、有効に活用できるように、
視野を広げ、柔軟に案件を進めていきます。
そして、弊所が強みとする医師面談などによって、
後遺障害診断書の記載方法など、医師に積極的に提案していきます。
どんな怪我でも、”まずは的確に第14級9号の認定を確保していく”
これが、弊所の強みであります。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故による”むち打ち”で首が痛くて手の中指が痺れる
むちうちの典型的症状
交通事故によるむち打ち症を受傷した場合の症状としては、
(A)頚部痛=首の痛み
(B)神経症状=腕や手の痺れ
が、典型的な症状かと考えます。
したがって、僕が、お客様に症状をお聴きする際は、
上記の症状を聞き逃さぬよう注意しています。
痺れの部位と医学的所見との整合性
手の”中指の痺れ”が出現した場合に、
その中指の痺れが、医学的所見(MRI画像・腱反射)と整合性がとれれば、
自賠責保険上の後遺障害等級の第12級13号の認定基準を満たすことになります。
具体的には、
手の中指が痺れる場合は、
(1)頚椎MRI所見=頚椎「C7」のヘルニア
(2)腱反射テスト=「上腕三頭筋」腱反射の低下または消失
(※ただし、腱反射については、初診時から症状固定時まで連続して所見が出続けていなければ、
自賠責側は評価をしない傾向があるように感じます。)
という所見を、後遺障害診断書に記載を得られれば、
後遺障害診断書上・医学的所見上は、第12級13号の認定基準を満たすことになります。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
12月は魔の月?
クリスマスソングが街に溢れ始めました。
なにか気持ちがそわそわする時期ですよね。
年末に向けて終わらせるべき仕事のこと、
楽しみなイベントのこと、
はたまた来年の目標、希望、
もしかしたら不安を抱えている方もいらっしゃるでしょう。
不安を抱えているという点は弊所も同じです。
弊所では、毎年12月は、後遺障害申請はしません。
症状固定を迎え、
後遺障害診断書やその他書類が全て揃っていても、です。
理由は、
弊所の経験上、
12月に入ると、
自賠責側の後遺障害審査が杜撰・曖昧になる傾向が強くなり、
慎重な審査もせずに、非該当で回答をしてくる、という事案を肌で感じたことがあるからです。
ここを、なんとなく、の感覚でも察知することがなく、
12月中にまとめて、
「えいやー!!」で後遺障害申請をしてしまい、
残念な結果を見せられる「他社様に依頼している被害者様」が少なからず出てきてしまう…
弊所はこの不安があります。
したがって、弊所ご依頼者には、
上記、事情を説明して、年明けの申請にさせていただいております。
ご依頼者には、
時間と労力とお金をご用意いただいて、
週3~4回に及ぶ定期通院をしていただいたわけですから、
慎重かつ適切な審査をしていただいた上で、
後遺障害等級審査の回答を出して欲しいものです。
こちらがわ(行政書士など)の
”簡単な申請時期の見誤り”で、
そんなところまで???
慎重であるのが、弊所の強みでもあります。
ちなみに、8月も要注意です。
※8月・12月に関する上記意見は、あくまで弊所独自のものです。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
コラムの更新を開始いたします
弊所の新しい「交通事故・後遺障害申請専門サイト」を公開して、1ヶ月ほどが経過いたしました。
とてもキレイなサイトにリニューアルできたので、
うれしい限りです。
さて、コラムでは、
・サイト本編で案内が足りなかった部分
・弊所の最新情報
・後遺障害申請の最新情報
などを公開していこうと思います。
ワードプレスの操作には、まだまだ不慣れな部分も多いですが、
温かい目でお付き合いをよろしくお願いいたします。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。