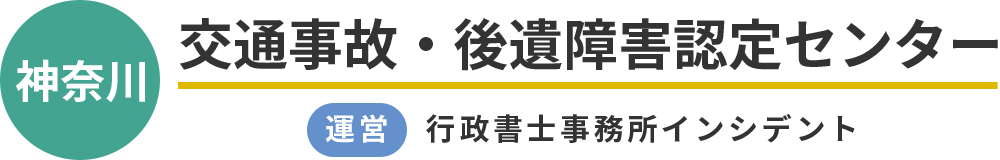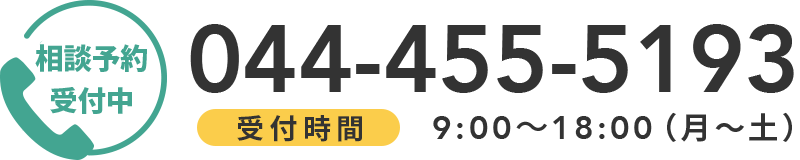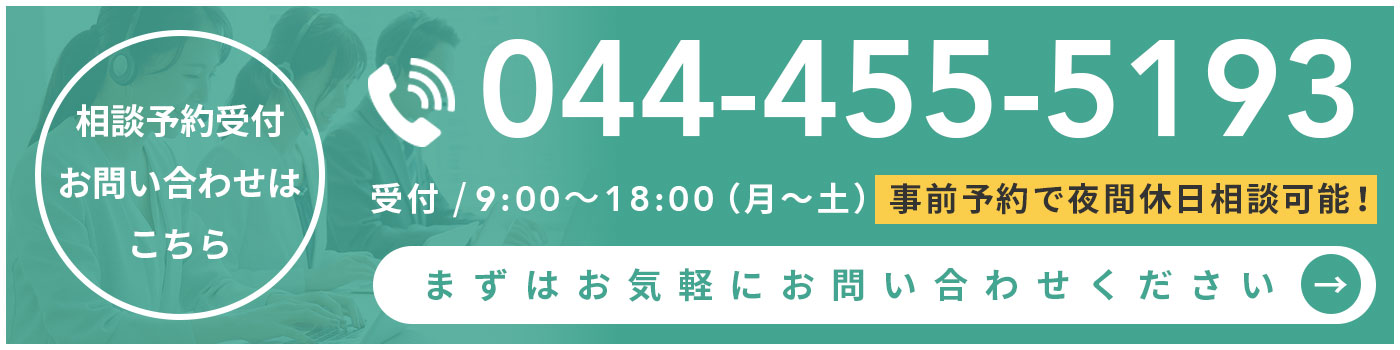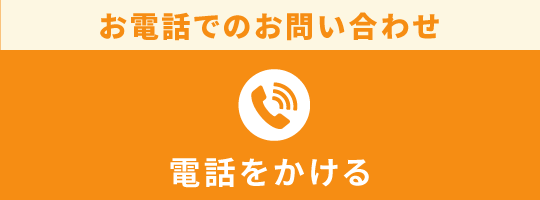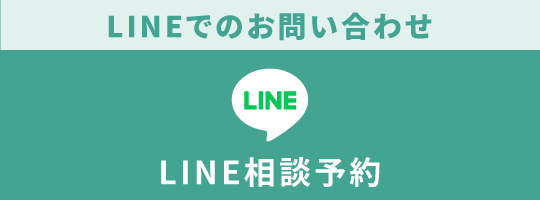Author Archive
交通事故による鎖骨骨折で骨折部と手術の傷痕が痺れている。これは後遺障害?
鎖骨骨折の後遺障害等級は4パターン
鎖骨骨折部の痛みについては、
自賠責保険上の後遺障害等級に該当する可能性があります。
弊所の鎖骨骨折を受傷したご依頼者のケースでは、
(A)機能障害:3/4以下の可動域制限>第12級6号
(B)変形障害:第12級5号
(C)神経症状:局部に神経症状を残すもの>第14級9号
(D)非該当
の4パターンが多いです。
「骨折=後遺障害等級認定」の絶対保証はありません
鎖骨骨折は手術対応になることがあり、
鎖骨の癒合、つまり骨がプレート等でしっかりつながり、
プレートの除去を終えれば、
月1回程度の定期診察の指示となることが多いです。
これでは、実通院日数が少なすぎて、14級9号さえ認定されません。
鎖骨骨折の場合はまず神経症状を狙う
弊所のご依頼者のケースでは、
3/4以下の可動域制限による後遺障害等級認定を得たケースはありますが、
こちらのご依頼者は、
(A)手術後の月1回の定期診察
(B)月10回程度のリハビリを継続しておりました。
実のところ、鎖骨骨折の場合は、可動域制限を残すことは少ないようです。
ただし、手術後の鎖骨部に痛みは残存することがありますので、
”局部に神経症状を残すもの”、として自賠責保険上の後遺障害等級第14級9号の可能性を残しながら、事案を進めていくことが重要です。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故による腰椎捻挫を受傷した場合の後遺障害等級は?
むちうちを受傷すると、同時に腰も痛めることが多い
交通事故により、
腰椎捻挫、
腰部挫傷、
腰椎椎間板ヘルニア、
などを受傷した場合に該当し得る自賠責保険上の後遺障害等級は、
(A)局部に”頑固な”神経症状を残すもの:第12級13号
>症状の根拠がMRI画像・腱反射など医学的所見で”証明”できるもの
(B)局部に神経症状を残すもの:第14級9号
>症状の根拠が受傷態様、治療経過などから医学的所見で”説明”できるもの
(C)非該当
と3パターンとなります。
「腰部痛」も認定対象となる「神経症状」です
弊所のお客様は、
(B)の局部に神経症状を残すもの、第14級9号が多いです。
そして、この第14級9号については、
腰椎捻挫後に、”痺れ”が出現していない場合でも、
腰部痛という”痛み”も、局部の神経症状が残存しているとして、
認定される可能性はあります。
つまり、「”痺れ”の出現=後遺障害等級認定を得る」、
という公式はない、ということをご理解ください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
むちうち受傷後の痺れの出現の部位
むちうちは、首の痛みだけではない
むちうち受傷後に、
腕や手に痺れが出現することがあります。
これは、神経学的に、
頚椎から上肢(腕・手)に神経がつながっているためで、
頚椎の損傷部位によって、
痺れが出現する部位に違いがあります。
具体的には、
頚椎C5=腕の内側
頚椎C6=親指・人差し指
頚椎C7=人差し指・中指
頚椎C8=薬指・小指
となります。
症状と頚椎ヘルニア部位とが合わないこともある
ただし、現実的には、
痺れの部位と頚椎ヘルニア部位に整合性がとれない場合があります。
したがって、頚椎MRI検査結果に、一喜一憂する必要はないと考えます。
弊所では、各精密検査結果を、
後遺障害診断時に、有効に活用できるように、
視野を広げ、主治医先生と相談の上、柔軟に医学的所見の収集を進めていき、
まずは第14級9号の認定を確保していく。
これが、弊所の強みであります。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故による肩の怪我と自賠責保険上の後遺障害等級の関係
肩の怪我はバイク好きの方に多い
弊所のご依頼者で経験しているのは、
診断名からすると、
(A)肩部打撲、
(B)鎖骨骨折、
(C)肩鎖関節亜脱臼、
(D)腱板損傷(腱板断裂)
が多いです。
後遺障害等級の認定を得たご依頼者の症状としては、
・痛み
・可動域制限
・鎖骨部の変形障害
となります。
肩関節はむちうちと同じくらいに難しい
弊所ご依頼者の認定例を、自賠責保険上の後遺障害等級別からみると、
(1)非該当
(2)神経障害
(3)機能障害(3/4制限又は1/2制限)
(4)変形障害
の4パターンがあります。
肩関節は、可動域制限・変形に限らない
ここで、注目すべき点は、
肩関節部の後遺障害等級としては、
(A)可動域制限による機能障害、
(B)変形障害、
のみならず、
”痛み”の残存も後遺障害等級第14級9号に該当する可能性があるという点です。
肩、ひじ、手首、股関節、膝、足首などの”関節系”は、
「可動域制限があることが後遺障害等級の条件である」というのは間違った情報であると考えます。
弊所は、ご依頼者の怪我が関節系の場合は、
当然、まずは機能障害・変形障害を想定します。
しかしながら、可動域制限などが残存しない場合は、
”痛み”が残存したことによる”神経障害”第14級9号の認定を得られるような戦略で進めていきます。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故による肩腱板断裂を受傷した場合の後遺障害等級は?
自転車・バイク事故に多い肩関節の怪我
弊所のご依頼者のケースでは、
自賠責保険上の後遺障害等級第10級10号の認定を受けたケースがあります。
事故態様としては、
ご依頼者が自転車で直進中、
右方から相手方自動車に衝突されたものです。
事故時の第一次診は大きな病院を受診しましたが、
第二次診は、ご依頼者のかかりつけの整形外科を受診しました。
診断名は、
第一次診では、肩挫傷、
第二次診は、肩鎖関節亜脱臼と腱板損傷、
というものでした。
相手損保会社を通す「事前認定」はおススメしません。
そして、6ヶ月間の通院を経て、
相手損保会社を経由しての”事前認定”を実施したところ、
”非該当”の通知が届きました。
MRI画像にブレがありよく審査ができなかったことが非該当の理由
その後、ご依頼者の主治医先生からのご紹介で、
異議申立案件としてご依頼をいただきました。
受任後は、それまでの診断書などの確認したところ、
肩関節のMRI画像報告書に、
”体動によるアーチファクト(画像のブレ)”があるため、
腱板の診断が不安定な状況という所見でありました。
そこで、MRI撮影時に動かないように注意していただき、
再度MRIを撮影していただきました。
非該当から10級への変更認定を勝ち取る
このMRI検査所見をもとに、
異議申立を実施したところ、
結論として、
(1)肩部に外傷性変化が認められる。
(2)腱板断裂が認められる。
(3)1/2以下の可動域制限を認める。
との理由により、
自賠責保険上の後遺障害等級第10級10号の認定に至りました。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故の怪我の治療中にまた交通事故…
むちうちを受傷し、またむちうちを受傷した
難しい手続用語ですが、
弊所が経験した交通事故賠償分野の異時共同不法行為の例です。
追突事故によりむちうちと腰椎捻挫を受傷し、
その怪我の治療中に…
また追突事故に遭い、むちうち・腰椎捻挫を受傷してしまう案件でした。
このケースでは、
(1)二事故目の相手損害保険会社に対応が引き継がれました。
その後、
(2)一事故目と二事故目の受傷部位が同じであるため、
むちうちと腰椎捻挫後の症状がどちらの事故が原因か不明と主張され、
二事故目の相手損害保険会社から治療費が打ち切られました。
(3)本ケースでは、労災保険案件でもあったため、労災保険に切り替えました。
弊所の強みの一つ。整形外科を紹介
もとの通院先の整形外科の主治医先生が、
相手方からの治療費を打ち切られ、
自賠責保険が使えなくなると、
途端に、不機嫌になり、対応が悪くなりました…。
そこで…
労災保険切り替え後、弊所でお世話になっている整形外科へ転院し、
治療を継続し、MRI検査を受診し、
後遺障害診断のための医学的資料の収集に専念しました。
そして、
一事故目から約11ヶ月後、
二事故目から8ヶ月後に、
主治医先生に症状固定の判断をいただき、
後遺障害診断書の作成をしていただきました。
異時共同不法行為の場合、一事故目と二事故目の自賠責会社に送付
この後遺障害診断書を基に、被害者請求をしていくわけですが、
異時共同不法行為の際の自賠責保険上の被害者請求は、
「一事故目」と”二事故目”の相手方自賠責会社へ請求をします。
そして、この請求には工夫が必要です。
当然、本ケースも、一事故目と二事故目の相手方自賠責会社へ後遺障害等級申請書類を送付し、
被害者請求を実施しました。
「二自賠」で認定されると「二倍」の自賠責金額の補償
後遺障害等級が認定された際の保険金の支払いについても、
自賠責保険に関しては、異時共同不法行為は特徴的です。
本ケースについて案内すると、
一事故目と二事故目の”両方”で後遺障害等級が認定されましたので、
一事故目:14級認定=75万円の自賠責保険金の支払い
二事故目:14級認定=75万円の自賠責保険金の支払い
計150万円の自賠責保険金を受け取ることができました。
いわゆる、”二自賠(にじばい)”と呼ばれる保険金請求方法です。
この二自賠がありますので、
交通事故のお客様との最初の面談の際は、
これまでの事故の経歴の有無や、
後遺障害等級認定の有無を、
注意深く聴き取りしなければなりません。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
自賠責保険上の後遺障害認定と通院の日数
トータルは90回。でも接骨院に偏っている。
弊所のご依頼者で、
整形外科などの医療機関への通院回数が少ないながら、
後遺障害等級認定を得たケースは、
事故日から症状固定日まで、
(A)整形外科=22回
(B)接骨院=68回
計90回というケースがあります。
合計でみれば、
たしかに、十分な実通院日数ではありますが、
整骨院への通院に偏っていました。
後遺障害等級認定のハードルはかなり上がった10年
本ケースは、約10年前の交通事故で、
この時期は、このような通院方法でも、
後遺障害等級として評価されることは多かったと感じます。
しかしながら、2023年現在は、
・事故から6ヶ月超の通院期間は必須
・実通院回数は合計90回が目安
・整形外科を基礎に通院をし、
・症状固定まで一貫すること(転院は少ない方が良い)
が重要であると感じます。
もちろん、接骨院の通院も、
後遺障害等級の評価として、カウントされますし、
一つの有効な所見ではあると考えます。
ご依頼者の生活もある。だからこそ、一緒に通院スタイルを決めていきます
ここが難しい点ですが、
ご依頼者には、交通事故治療の他に、仕事や家事、子育てなど、
別の活動がたくさんあります。
そして、整形外科の診療時間は午後6時〜7時に閉まることが多く、
整形外科への通院を、ご依頼者のスケジュールに組み込むことが困難なケースがあると思います。
これらの諸事情は、弊所も把握しているため、
ご依頼者と調整とご理解をいただいた上で、
一緒に通院方針は決めていきたく思います。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故でむちうち・腰椎捻挫を受傷し、ヘルニアが発覚したが、後遺障害等級が認定されない人とは?
主な理由5つ
理由としては、
(1)6ヶ月間の通院がない(事故から6ヶ月未満に症状固定にしてしまった)
(2)通院回数がとても少ない
(3)通院が「接骨院」に偏っている
(4)後遺障害等級を受けたことがある
(5)本件事故とは関係ないヘルニアの治療歴がある
というのが、すぐに思い当たる理由です。
(1)と(2)と(3)については、
後遺障害等級として評価されることは「少ない」又は「ない」と考えます。
後遺障害等級の認定を受けたことがある場合でも・・・
(4)については、
前回の事故と今回の事故とで、
(A)診断名が重ならない
(B)症状が重ならない
などであれば、今回の事故でも後遺障害等級として評価されることはあります。
つ・ま・り、
例えば、
前回の事故の症状:頚部痛
今回の事故の症状:右手の痺れ
など、今回の事故後の新たな症状として「右手の痺れ」が出現したことが証明できれば、
その右手の痺れの症状について、
ピンポイントで後遺障害等級の認定評価をいただける可能性もあります。
これは、(5)本件事故とは関係ないヘルニアの治療歴がある場合も同様であると考えます。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
後遺障害等級認定と「通院の空白」
弊所は「異議申立」も積極的にサポートします
最近の弊所のご依頼者のケースからすると、
(1)最初の症状固定
↓
(2)後遺障害等級申請
↓
(3)非該当
↓
(4)異議申立申請に関して弊所で受任
↓
(5)弊所でお世話になっている整形外科をご紹介をし、通院加療を再開
↓
(6)二回目の症状固定+後遺障害診断
↓
(7)異議申立申請
↓
(8)第14級9号への変更認定
というケースがありました。
症状固定後も通院継続がおススメ
こちらのご依頼者は、(1)の症状固定から(5)の通院再開まで、
”4ヶ月程度”の通院の中断がありました。
ただし、このケースは、
(1)最初の症状固定日までの実通院日数が十分であったこと
=事故から約6ヶ月の間に、約80日の実通院日数がありました。
(2)通院先が”整形外科のみ”と必要最小限であったこと
などの諸要素がうまく作用したことが要因であると考えています。
しかし、当然のことながら、
通院の中断があるお客様のすべてが当てはまるわけではありませんので、
ご注意ください。
通院の中断は「治療費打ち切り」の対象にもなる
そして、補足ですが、
事故後、通院を開始したものの、
(A)通院のペースの間隔が大きかったり、
(B)通院が1ヶ月程度なかったり、
(C)接骨院への通院に偏っていたり、
などの諸事情があると、
後遺障害等級「非該当」の対象となる前に、
治療費の打ち切りの対象にもなり得るので、
この点もあわせてご注意ください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故により肩を怪我して、鎖骨がボコッとしてる?
鎖骨骨折には神経障害、機能障害、変形障害がある
タイトルの症状からは、鎖骨の「変形障害」が想定できます。
弊所のご依頼者のケースの事例でありますが、
鎖骨骨折は、
・神経症状(14級・12級)
・機能障害(12級・10級)
が真っ先に当てはまる後遺障害ですが、
”体幹骨(鎖骨)に著しい変形障害を残すもの”として、
自賠責保険上の後遺障害等級第12級5号も当てはまります。
肩鎖関節脱臼の診断名で14級認定
本件事故態様としては、
ご依頼者がバイクで直進中、
左方から進入してきた相手方自動車に衝突されたものです。
診断名としては、主に、肩鎖関節脱臼であり、
症状としては、
・痛み
・可動域制限
でした。
事故から約8ヶ月後、症状固定とし、
後遺障害等級申請(弊所受任前であったため事前認定)をしたところ、
”局部に神経症状を残すもの”として、
第14級9号の認定でした。
14級で納得いかない。ご依頼者は異議申立を希望
その後、
弊所が異議申立申請案件として、ご依頼をいただきました。
受任後は、弊所でお世話になっている整形外科の紹介をいたしました。
本件ご依頼者は、最初の症状固定日から通院を止めてしまったため、
ご紹介した整形外科に、
改めて6ヶ月間通院していただきました。
そして、約6ヶ月の通院後、
主治医先生に、症状固定のご判断と改めて後遺障害診断の再評価をしていただきました。
レントゲンで変形がわかっても足りない
ここからがポイントですが、
主治医先生作成の後遺障害診断書に加えて、
お客様の協力を得て、
”裸体時の鎖骨部の写真”を撮影していただきました。
理由は、変形障害の認定基準として、
レントゲン所見による変形が明らかになることだけでは足りず、
”裸体となったとき、変形が明らかにわかる程度のもの”をいう、
というのが、認定基準にあるからです。
よって、異議申立申請の際は、
(1)後遺障害診断書
(2)裸体時の鎖骨部の写真
(3)弊所作成の異議申立書
を基礎として、申請をしました。
結果として、狙い通りの、体幹骨(鎖骨部)の変形障害として、
第12級5号への変更認定を得ました。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。