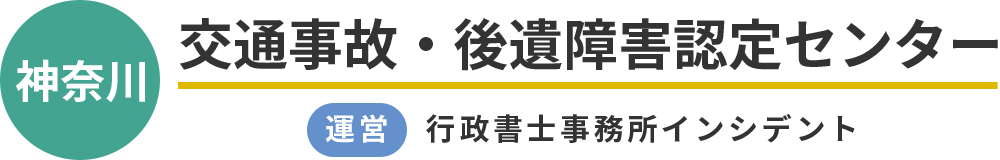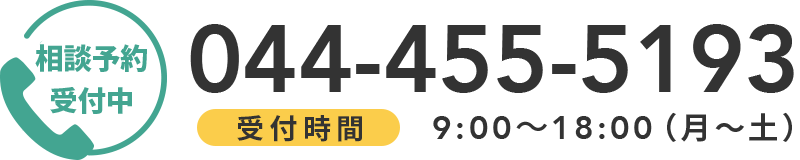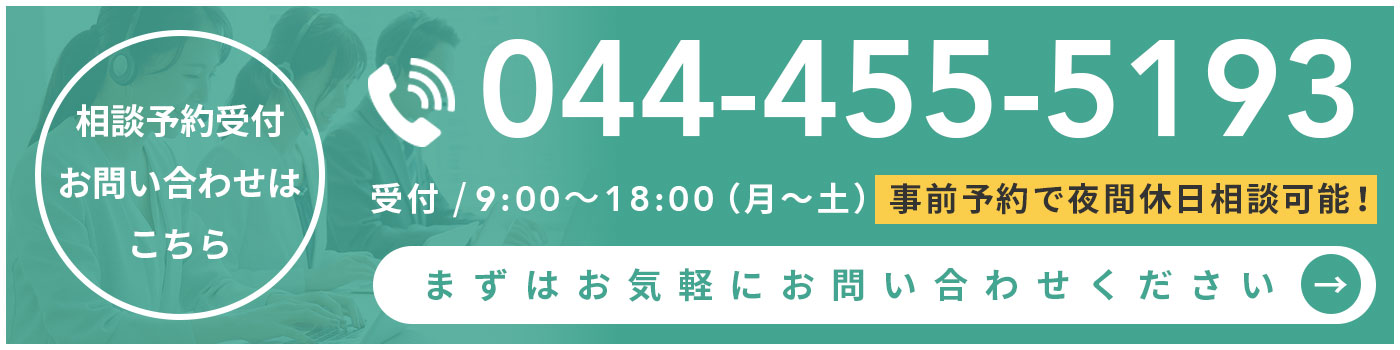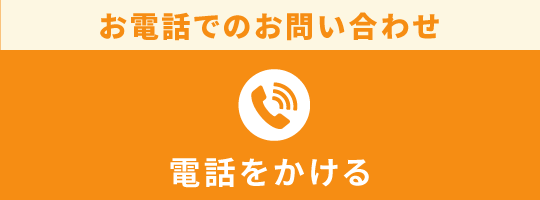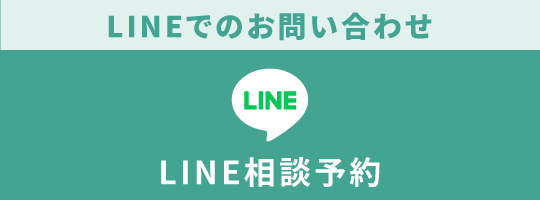自賠責保険制度について
通院の中断について(交通事故・後遺障害)
通院の中断は不利になる
交通事故による怪我の治療は、1ヶ月(=30日)程度の中断があると、
治療費の打ち切りの対象になる可能性が高まります。
この1ヶ月以上の中断は、
(A)仕事や家事、学業で忙しくてやむを得ず通院できなかった、という事情もあれば、
(B)主治医先生の指示で、「次回は1ヶ月後に診せてください」という指示による場合もあります。
(B)の具体例としては、鎖骨骨折の実例を思い出します。
鎖骨骨折は、交通事故後、手術対応になりプレート固定術が行われることがあります。
その後、骨癒合が確認でき次第、プレート除去手術となるのですが、
プレート除去後は、医師の指示で「月1回程度の診察」に切り替わることがあり、
その間、リハビリの指示もありませんので、
医師の指示にそのまま従うと、1ヶ月の通院の空白ができるケースがあります。
これは、治療費打ち切りの対象にもなりますし、
後遺障害審査上も通院の空白ができるということは連続性・一貫性が途切れることになりますので、
非常によくない状況となります。
連続性と一貫性を好む自賠責保険
交通事故による怪我の治療を6ヶ月超、相手損保会社に補償をいただけた実例をみますと、
いずれも、週2~3回の通院ペースを維持しているのが特徴です。
これは、医療機関・整形外科から相手損保会社に毎月届く診断書や診療報酬明細書から、
・通院のペース
・治療の内容
を確認し、被害者の、「怪我を回復させようとする努力がある」と判断していただいているおかげでもあります。
一方、通院のペースにばらつきがあったり、通院のペースが落ちてくると、
「治ってきた」という判断を診断書等の書面で判断され、
治療費の打ち切りの対象者にされるのであろうと察します。
症状固定後も通院は継続すべき
そして、弊所に異議申立のご相談者に多いのが、
症状固定を迎えた日に、通院をすべて止めてしまっていることです。
通院のペースは週1回や2週間に1回としてもよいので、
後遺障害等級申請の結果を確認し、被害者自身が納得するまでは、通院は継続することが最善です。
初回の後遺障害等級申請で、認定となるのは一番ですが、
初回は「非該当」である可能性もあります。
非該当の結果に対して、異議申立申請を試みる際、
「症状固定後も通院を継続していること」が、とても重要な新たな医学的所見になります。
症状固定後も通院を継続していることにより、
症状が重篤で、その症状に苦しめられている、ということをアピールすることができます。
6ヶ月超の、週3回の通院は本当に疲れることと思いますが、
症状固定を迎えて終わりではありません。
むしろ、新しいスタートになります。
交通事故賠償問題に真剣に取り組むとなると、かなりの根性が必要になります。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故証明書の取得(自賠責保険・後遺障害)
交通事故後は「交通事故証明書」を取得しましょう
交通事故証明書は、公的に本件事故があったことを証明する資料で、
生命保険、損害保険、自賠責保険の請求時には、必須となる書類です。
この交通事故証明書は、
(A)相手方損保会社から取得
(B)警察署や交番で交通事故証明書取得払込取扱票にて郵便局から申込・取得
(C)自動車安全運転センターのHPからネット申込・取得
のいずれかの方法で取得ができます。
ただし、当初は「物件事故」で処理したものを、後日、人身事故に切り替えた場合は、
人身事故扱いにデータ反映されたか否か、管轄の自動車安全運転センターに確認の上、
申込をしたほうが良いです。
交通事故証明書申し込みは簡単
弊所では、(B)の払込取扱票にて郵便局から申込をすることが多いです。
この払込票には、記載箇所がたくさんあるように感じますが、
すべて記載する必要はありません。
記載すべき必須項目としては、
(1)事故種別
(2)発生日(事故日)
(3)取扱警察署
(4)申請数(何通欲しいか)
(5)当事者の氏名(申請者側のみでOK)
(6)申請者と当事者の続柄(本人の場合は「本人」)
(7)申請者連絡先
(8)申請者の住所・氏名
となります。
※結局、記載箇所が多いですね…。
面倒な自賠責保険請求の書類収集
弊所は、自賠責保険請求のお手伝いをこれまでサポートしてきたので、
・必要書類や記入の仕方、
・必須書類が取得できない場合の代わりの書類、
などアイデアやノウハウが積み重なっているので、臨機応変に対応できます。
しかし、交通事故証明書1通取得するにもそれなりに面倒な作業であるようにも感じます。
特に、自賠責保険の被害者請求の肝となる、
(A)自賠責保険書式の診断書
(B)自賠責保険書式の診療報酬明細書
(C)自賠責書式の後遺障害診断書
の作成を医療機関に申し込む際には、
・診断名
・入院期間や通院期間(いわゆる「証明期間」といいます)
・医学的な所見(症状、画像所見、神経学的所見)
など、いつからいつまでの、どういった診断内容の記載が最善なのか、
がわからないと思います。
自賠責側は、診断書の記載内容のたった一文を持ち出して、非該当と判断することもあるので、
細心の注意が必要でもあります。
弊所では、自賠責保険の被害者請求に必要な書類、1通の取得からお手伝いいたしますので、
交通事故、自賠責保険請求でお困りかたは、行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
弁護士選びを間違えているかたへ(交通事故・後遺障害)
「交通事故問題=弁護士」がそもそも間違いです
交通事故による賠償問題やトラブルは、弁護士に相談や依頼をするという思い込みがまず間違いです。
交通事故の問題にも様々なものがあります。
・相手方損保会社担当者が高圧的で電話で話をしたくない
・相手損保会社が治療費を出さないと言っている・・・
・相手損保会社から治療費を打ち切りと言われたがどうすればいいのか
・事故の怪我で身体がツラいため仕事に行けない。休業損害はどうなるのか
・過失割合はどう決まるのか
・後遺障害等級認定を受けたいがどうしたらいいかわからない
・慰謝料をたくさん貰いたい
などなど、被害者ごとに視点が違うので、悩みや不安も千差万別です。
これら交通事故の問題のすべてについて、弁護士が強いわけではありません。
弁護士が強いのは、
(1)相手方に損保会社が付いており、
(2)過失割合が決まっていて、
(3)後遺障害等級が認定されている、
案件です。
こういった案件は、あとは慰謝料計算式に当てはめて、定型的に示談交渉をすればよいですし、
受任から損害賠償金の回収が比較的早く、売上の構築が早期となるため、
弁護士はとても好みます。
つまり、逆をいえば、
・相手方に損保会社が付いていない、
・過失割合が不明確、
・後遺障害等級が認定されるかも不明確、
のような案件は、交通事故専門弁護士といいながら、弁護士自身がどうしたらいいのかわからないようなので、弁護士が受任後は、無駄に時間が過ぎ、適切な症状固定の時期を失い、
ただ後手に回るだけです。
弁護士は、弁護士費用特約から着手金をもらえれば満足なわけです。
このような対応が、交通事故に強い弁護士・法律事務所といえるでしょうか?
弁護士は後遺障害等級が認定された「後」が出番
そもそも、弁護士は、後遺障害等級認定申請は得意としていません。
医師面談もしなければ、診断書の記載内容のチェックもしません。
定型句のように、弁護士からご依頼者には、
「たくさん通院してください」
「症状固定になったら教えてください」
「後遺障害診断書を取得したら事務所に送ってください」
という案内をするのみ。
なぜ、たくさん通院するのがよいのか?
適切な症状固定時期はいつなのか?
後遺障害診断書にはなにを書いてもらえれば等級認定に近づくのか?
というところが不安でわからないから、弁護士に依頼しているのに、
依頼をした意味をなさない弁護士がたくさんいらっしゃいます。
弁護士は、とにかくたくさん依頼を受けたいから、とにかく受任してしまえという傾向が強いです。
弁護士は、後遺障害等級申請の詳細は知らないことが多いです。
弁護士は、後遺障害等級申請結果が出てからが出番です。
もっというと、後遺障害等級認定を受けた後は、
被害者自身が「交通事故紛争処理センター」に調停申し立てすれば、
無料で、弁護士基準で示談に至ることもあるので、
極論、交通事故賠償問題で弁護士の役割はありません。
交通事故賠償問題を左右するのは、後遺障害等級認定の有無です。
この後遺障害等級申請は、行政書士が圧倒的に強いです。
交通事故賠償問題は、「行政書士の選択」「医療機関の選択」でほぼ解決が決まります。
いまの弁護士から弊所へ切り替え
現在の弁護士が、頼りない場合は、行政書士事務所インシデントに依頼を切り替えてください。
事件を前に進めることができない弁護士に依頼をし続けても、
時間とお金と労力を浪費するだけで、早期解決に至りません。
交通事故賠償問題は、多くの時間をかけることで、慰謝料が増額するわけではありません。
早期に、適切な賠償金で解決を希望する方は、
行政書士事務所インシデントへお問い合わせください。
行政書士事務所インシデント LINE公式
https://lin.ee/g4ZxkOz

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故は行政書士に依頼する(自賠責保険・後遺障害)
交通事故の相談はまず行政書士が最適です
以前のコラムでもご案内しましたが、交通事故は、追突事故が多いです。
そして、この追突事故で怪我する部位は、首と腰です。
いわゆる「むちうち」です。
このむちうちは、
(A)事故から3ヶ月程度で症状が改善し示談する場合
と
(B)6ヶ月超の通院と後遺障害等級申請をする場合
の2つのパターンが考えられます。
そして、(A)の3ヶ月程度で症状が改善し、示談する場合のほうが多く、
こういった事案は行政書士に依頼するほうがメリットがあります。
弁護士に依頼するメリットは少ない?
事故から3ヶ月程度で治療を終了し、示談とする場合の被害者側が受け取れる「通院慰謝料」は、
弁護士基準=約53万円
自賠責保険基準=満額38万7000円(90日×4300円)
が目安です。
この金額を踏まえて、弁護士に依頼する場合と行政書士に依頼する場合のメリット・デメリットをみていきます。
弁護士に依頼する
【メリット】
・弁護士基準での慰謝料請求となり、自賠責保険基準より高額な慰謝料をもらえる
・交渉は弁護士がすべてやってくれる
・弁護士費用特約があれば、被害者が弁護士報酬を払う必要はない
【デメリット】
・弁護士費用特約から弁護士へ着手金支払後は、弁護士の対応が遅くなる・無くなる
・対応が遅くなるため、示談まで時間がかかる
・弁護士の交渉力が弱い場合は、弁護士基準で示談できない
・被害者に過失があれば減額される
一方、自賠責保険基準+行政書士に自賠責保険請求手続を依頼する
《メリット》
・自賠責保険からの支払が早い(※請求から支払いまで約1ヶ月ほど)
・交渉がない(被害者自身で自賠責保険請求する際も交渉事がないのでストレスが少ないです)
・行政書士への報酬が安い
※自賠責保険から補償された保険金額から行政書士への報酬の支払いとなります。
(おおよそ行政書士書面作成費用として3~5万円)
・過失減額がされない(被害者に70%以上~100%の過失がある場合に順次減額)
《デメリット》
・弁護士基準に比べて補償される通院慰謝料が低い
※先述の例ですと、弁護士基準53万円ー自賠責保険基準38万7000円=14万3000円の差があります。
・経済的に苦しい方は、診断書の取得費用が用意できない。
※被害者自身で診断書などを取得をする必要があり、被害者が文書取得費用の一時的な立替があります。
・120万円の上限がある
医療費などのの補償額が大きい場合は、慰謝料が少なくなる可能性があります。
それぞれのメリット・デメリットの感覚は、
被害者自身の感性ですので、被害者がお好きな方を選択するのが良いです。
後遺障害等級申請は圧倒的に行政書士が強い
交通事故による自賠責保険の後遺障害等級申請は、
圧倒的に行政書士が強いです。
交通事故の損害賠償の明暗を分けるのは「後遺障害等級認定」。
この自賠責保険の被害者請求、異議申立申請は、
行政書士の方が、主治医先生との信頼関係構築に向けた医師面談をしたり、後遺障害診断書の記載内容の修正や削除訂正依頼など、熱心に活動をいたします。
交通事故賠償問題は、
「通院する医療機関」と「後遺障害等級の有無」で決まります。
この根幹となる後遺障害等級認定を勝ち取ることができれば、
良い解決に通じます。
交通事故の損害賠償請求、後遺障害等級申請の分野は、
まず行政書士に相談した方が、最適かつ最速で解決に結びつきます。
交通事故賠償事案が弱い弁護士に相談・依頼をしないよう気を付けてください。
弁護士費用特約からの着手金目的の弁護士も多数おりますので、ご注意ください。
交通事故・自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。
行政書士事務所インシデント LINE公式
https://lin.ee/YtfZPJJ

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
相手方が「自転車」の場合(交通事故・自賠責保険)
「自転車」のそれぞれ
自転車と呼ばれる乗り物が複数あります。
(A)一般的な自転車
(B)原動機付自転車(いわゆる「原付」)
(C)ペダル付き原動機付自転車(最近話題の「モペット」)
(D)電動キックボード(これも最近話題の「LUUP」):特定小型原付
と4種類が挙げられます。
これら、自賠責保険加入義務があるのは、
(B)原付(原動機付自転車)
(C)モペット(ペダル付き原動機付自転車)
(D)LUUP(電動キックボード)
となります。
相手方が「自転車」であっても自賠責保険が適用できる
したがって、その交通事故の相手方が(B)(C)(D)のいずれかであった場合は、
相手方の自賠責保険に請求をして、
(傷害部分)怪我の治療費・通院交通費・通院慰謝料など
(後遺障害部分)14級から1級までの後遺障害
(死亡事故)
に関する補償を受けることができます。
一般的な自転車も自賠責保険加入義務であるべき
最近は、(A)の一般的な自転車に衝突されたことによる、
・死亡事故
・約1億円の高額賠償判決
事案もありますので、
(A)の一般的な自転車も自賠責保険加入は義務付けるべきだと思います。
以前にもコラムで書きましたが、競技用自転車の運転者のマナーには怒りを覚えることがあります。
弊所の地元でもある多摩川沿いのサイクリングコースを散歩する方は、
本当にお気を付けてください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
書類の保管について(交通事故・自賠責保険)
弊所では、自賠責保険被害者請求後は自賠責保険側に、審査を円滑に進めてもらい、
できるだけ早く審査回答をご依頼者に届けて次の対策や提案をしたいと考えております。
そのため、書類の不備はできるだけないようにしたいので、
自賠責保険の被害者請求書類の準備には、
細心の注意を払いますので、神経をすり減らすこともあります。
この書類の不備を最小限にするためには、ご依頼者の協力も必要です。
そして、そのご依頼者の協力を得るためには、
事前のご案内をして、書類の保管をしてもらうことがポイントになります。
弊所が考えるご依頼者にしっかり保管して欲しい書類を2つ挙げます。
1.領収証・診療明細書
この書類は、意外にも破棄したり、紛失したりされることが多い書類です。
特に重要な場面としては、
交通事故の怪我の治療を「健康保険適用」とした場合です。
この時は、医療機関発行の領収証・診療明細書が、
自賠責書式の「診療報酬明細書」の代わりになるので、大切に保管していただきたいです。
2.診断書
これは本当に大切にして欲しい書類です。
自賠責保険は、「一貫性」と「連続性」を好みますので、
・交通事故受傷後の、
・初診医療機関で、
取得した診断書の診断名がとても重要になります。
医療機関から診断書取得後は、警察署や保険会社に提出することがありますが、
写真でもよいので、「写し」を保管していただけるととても助かります。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
医療照会のいろいろ(交通事故・自賠責保険)
自賠責保険に異議申立申請をすると、
「医療照会」というものが入ります。
これは、自賠責損害調査事務所という「後遺障害等級審査機関」が、
本件で被害者が通院をした「すべての医療機関・整形外科」に照会をかけます。
※接骨院は除きます。
この医療照会はパターンがありまして、頚椎捻挫・腰椎捻挫事案について、
弊所で経験をしたものを3つご紹介いたします。
1.原則的な医療照会パターン
各医療機関・整形外科に、
(A)頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について(A4書式)
(B)神経的所見所見の推移について(A3書式)
という2つの書類によって、医療照会を行うパターンです。
これが原則です。
2.診療録のコピーを送るパターン
これは、各医療機関・整形外科で保管している診療録(いわゆる「カルテ」)開示のパターンです。
この照会は、すでにある診療録をコピーして送るだけ、ですが、
難点があるように考えます。
詳細を知りたいかたは、ご依頼後にこっそり教えます。
3.医療照会なしパターン
このパターンは珍しいパターンです。
例外といってもよいと思います。
弊所で経験した「医療照会なし」パターンの事案は、
無事に、非該当から14級認定に至りましたが、
医療照会をしないで”ばっさり”と非該当判断という事案もあるように察します。
上記のように、交通事故の内容もいろいろで、同じものはないですが、
自賠責保険請求後の自賠責側の対応や審査もいろいろです。
弊所では、あまり先読みし過ぎず、
相手方の反応などをみて柔軟に、迅速に対応をすることも”時には”必要であると考えます。
交通事故による自賠責保険請求(後遺障害部分)にお困りの方は、
行政書士事務所インシデントまでご相談・ご依頼ください。
行政書士事務所インシデントLINE公式
https://lin.ee/X4WXcW3

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
完治は目指さず、痛みと付き合う(交通事故・後遺障害)
交通事故後の怪我は、たとえ後遺障害等級の認定に至らない怪我・症状であっても、
完治に至ることは少ないようです。
完治を目標としてしまうと、
精神的に疲弊してしまったり、自分で自分を追い詰めてしまったりする被害者もいるので、
注意をしていただきたいと思います。
加えて、完治を強く目指す被害者は、「ドクターショッピング」といって、
良い先生、良い治療、完全に治してくれる病院を探し回る状態に陥る被害者もおり、
これは、後遺障害等級認定の観点からみても悪い状態です。
少し私の話をいたしますと、
私自身、高校3年生の時に、交通事故ではありませんが、
膝の怪我(診断名としてはおそらく「膝蓋骨骨折」)をしまして、手術を受けた過去があります。
いまだに完治に至りません。
痛みは常にありますし、時折、階段の昇り降り時に痛みが増します。
(※手術直後の当時は階段の昇降が本当に恐かったため、
駅などの階段はいまだに手すりがある側を選んで歩いています。)
しかし、私の場合は、正座や胡坐、歩行、ランニングなどは”ある程度”支障がなくできますので、
それで良しとしています。
交通事故の怪我の治療・通院は、
(A)損害賠償請求のための通院
と
(B)身体の回復のための通院
を分けて考える必要があります。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
診療報酬明細書も重要です(交通事故・自賠責保険)
どんな治療をしたか、も重要です
自賠責保険の後遺障害等級の審査をする際、
(1)自賠責書式 診断書
(2)自賠責書式 後遺障害診断書
に記載されている医学的所見を基礎に審査が進められます。
これら診断書などに加えて「自賠責書式 診療報酬明細書」の情報も重要なため、
自賠責保険の被害者請求に、必要な書類です。
この診療報酬明細書には、
・受傷日、初診日、診療期間などの情報
・その月の通院日、通院日数の合計
・診断名
・診療内容
・その月の診療報酬請求額の合計と内訳
などが細かく記載されています。
後遺障害等級審査の際は、
「どんな治療をしたか」という「診療内容」も当然に審査対象になりますので、
診療報酬明細書の情報はとても重要です。
領収書・診療明細書は大切に保管
診療報酬明細書は、交通事故の相手方に損保会社があれば(=任意一括対応がある場合)、
相手方損保会社が、直接、医療機関とのやりとりをするため、
タイミングをみて、相手方損保会社に依頼をすれば、取得することができます。
しかし、交通事故の怪我で健康保険を適用した場合には、
「自賠責書式 診療報酬明細書」の取得ができないことがあり、
この場合は、医療機関発行の「診療明細書」で代替することがあります。
現在、交通事故の怪我で、健康保険適用で通院している方は、
医療機関発行の「診療明細書」を大切に保管してください。
交通事故を原因とする自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。
行政書士事務所インシデント LINE公式
https://lin.ee/HrlWVCs

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
自賠責保険の後遺障害認定の難しさ(交通事故)
自賠責保険の後遺障害等級認定は本当に難しいです。
弊所が考える難しい理由は複数ありますが、主要なもの3つご案内いたします。
1.通院期間の長さと通院回数の多さ
弊所で多くお手伝いする頚椎捻挫(=むちうち)に関する後遺障害等級認定のためには、
・事故日(治療開始日)から6ヶ月超の治療期間
・週3回・整形外科
というルールがあります。
6ヶ月間超の治療期間というのは、必須のルールなので、しかたがないにしても、
ここをクリアしないと「認定されるものもされない」されません。
ご相談時に、6ヶ月の治療期間と聞いて、弊所への依頼を断念されるご相談者もおります。
そして、週3回・整形外科という点も大変に厳しいルールです。
整形外科の診療時間は9時~12時、15時~18時というのが多く、
会社勤めの方など時間の拘束があるかたには本当に厳しいルールです。
加えて、この整形外科の診療時間内に週3回の通院は、追い打ちをかけるように厳しいルールです。
2.後遺障害診断書に記載すべきことが曖昧である
6ヶ月間超、週3回の整形外科の通院をクリアし、
いざ症状固定・後遺障害診断書作成の段階になったとき、
後遺障害診断書に、
・なにを
・どのように
書いてもらえばわからない、という状況に陥ります。
自賠責保険などの保険会社のホームページにも記載すべきことの正式な手引きはありません。
たしかにネット情報では、
”ある程度”後遺障害診断書に記載すべき医学的所見の案内がありますが、
それはそれで、その人の成功例です。
患者様ごとに、後遺障害診断書に、
・書くべきこと
・書くべきではないこと
があります。
3.審査が書面審査である
自賠責保険の後遺障害等級審査は「書面審査」が原則です。
書面でのみ判断されるため、
患者様の実際の症状やその症状で困っていることが、
後遺障害等級に反映されないことが多いです。
これは本当に苦しい、悔しい。
一方、労災保険の後遺障害等級審査は、
申請後、労災顧問医の審査(診察)が指定日に入りますので、
実際の症状と後遺障害等級とが噛み合うことが多いです。
自賠責保険の後遺障害等級審査も、申請後、医師の診察をして欲しいところです。
まとめ
上記のように、自賠責保険の後遺障害等級認定を勝ち取るには、
1.通院
2.後遺障害診断書への正しい記載
3.自賠責保険の書面審査
というの3つのルールを意識して、一つ一つクリアしていかなければなりません。
3つのルールをクリアすることは本当にツラく、長い闘いなります。
この闘いに真剣に向き合って、どんな解決でも納得するという覚悟も必要です。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。