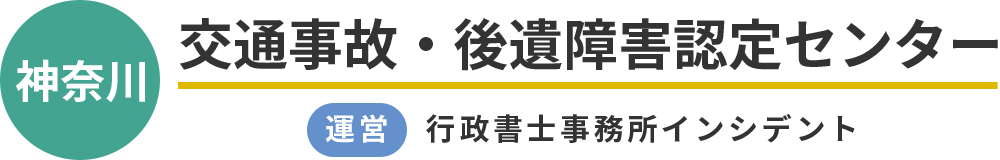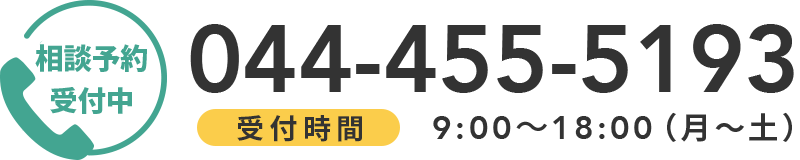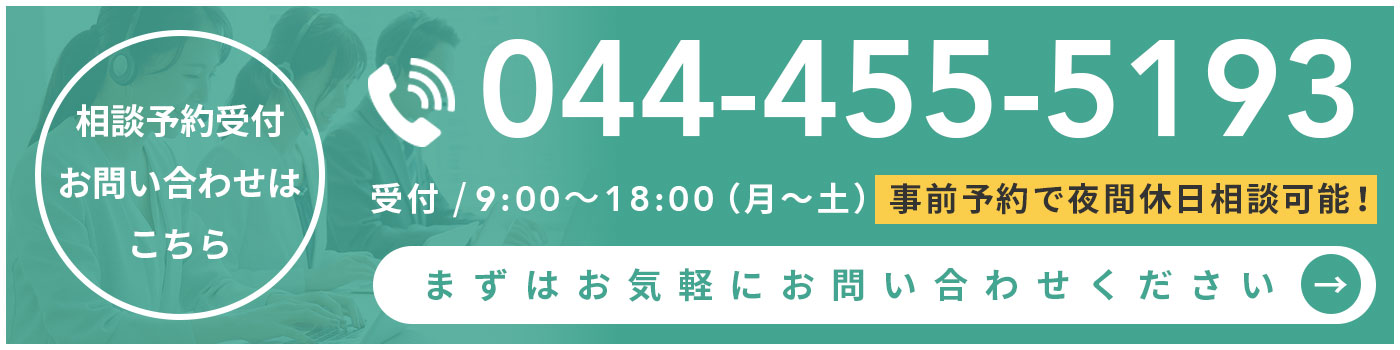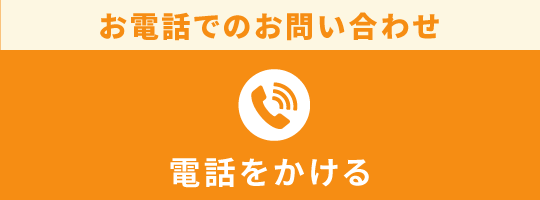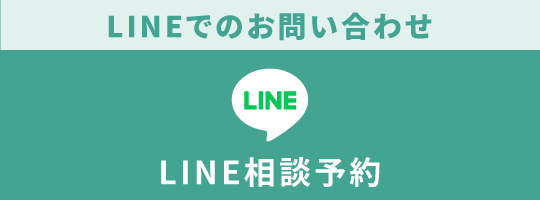Author Archive
ニッチ業務よりベタ業務を(交通事故・自賠責保険)
市場で売れてるもの、
流行りの業務を察知して、 真似して、
それから始めるのもいいと思います。
自分のやりたいことよりも、
売れてる商品を売る方が、
いろいろと乗れます。
確固たる自分の哲学も必要だけど、
シビアなそろばんも必要です。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
最近思うこと(交通事故・自賠責保険業務)
法令知識を貯めておくこと、
その知識を表現できること、
これは基礎だし、重要だけど、全てではない。
にも関わらず、 机に齧り付いて実務書や好きな本を読んでばかり。
ときには書を捨てて、外に出よう。
行政書士資格とバッジを振りかざしても、
お客様はこない。
創業当初は、売れることも大きな野望だったけど、
せっかく、自分の店を持ったのだから、
だめでも「思い出作りをしよう」と楽観的でもあり積極的だった。
初心を忘れていた今日この頃です。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
SNSはめんどくさい(交通事故関連情報)
このコラムを中心に、
各SNSに拡散しているのですが、
まれに、コメントをもらうことがあります。
正直言って、的外れなコメントもあります。
浅はかな経験と知識であることを感じます。
弊所も知らないことを日々学びながら実務にあたっています。
コメントをする前に、ご自身で、
自分の保有情報と知識を事前に調べてください。
あまりにも的外れなコメントには返信しないこともあります。
お互いに時間の無駄です。
まず、コメントいらないです。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
同じ事故はありません(自賠責保険・後遺障害)
診断名が同じ、
治療期間も同じ、
後遺障害等級申請に提出した資料も同じ、
でも、
A.後遺障害等級が認定される人
B.非該当の人
と自賠責側の評価が分かれることがあります。
理由としては、まず弊所が想定するのは、事故態様が違う、ということです。
例えば、同じ「追突事故」による頚椎捻挫でも、
相手方車両が、
徐行レベル?だったのか、
ノーブレーキ?だったのか。
同じ”頚椎捻挫”でも、
追突事故による被害なのか、
自転車乗車中の被害なのか。
上記のように、事故態様に二つと同じものはありません。
他にも、性別の違い、性格の違い、体格の違い、などなど、
全てが同じ、はないわけです。
局所ばかり見てはいけません。
大局を捉えて、視野を広く・大きく持って、
後遺障害等級申請準備・申請を進めていかなくてはなりませんよ。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
申請はだれがする?(交通事故・自賠責保険)
弊所が申請者でも後遺障害認定は受けています
自賠責保険上の後遺障害等級申請(異議申立申請)を、
お受けした場合、
弊所の名前で申請いたします。
稀に、ご依頼者から、
後遺障害等級申請に必要な書類を弊所で収集サポートをして、
↓
申請は、「○○法律事務所 弁護士○○」と、依頼している弁護士名でお願いします、という要望をいただきます。
理由はよくわかりませんんが、
弁護士の名前で申請した方が後遺障害等級認定を取りやすい???
といった程度の理由かな、と察します。
弁護士の名前だから必ず認定される保証はない
しかし、
「○○法律事務所 弁護士○○」で後遺障害等級申請をしても、
非該当になる時は非該当になります。
これは実際にあります。
現時点の弊所の見解では、
自賠責側が弁護士に対する忖度がないようで、この点、自賠責側が好きです。
弁護士の申請で「非該当」であったために、
弊所に異議申立申請の相談・依頼がくるので、
申請者が弁護士だからといって、認定率が高い・上がるわけではありません。
この点、よく覚えておいてください。
ご依頼者と意見が合わなければ辞任します
後遺障害等級申請に必要な書類だけ集めて、
申請は弁護士の名前でお願いします、と言われると、本当に憤りを感じます。
こういったことがあると、
本当に残念な気持ちになり、悲しくなり、
サポートをやめたくなりますので、今後は辞任します。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
後遺障害認定の専門家に依頼するメリット
弊所に依頼するメリットを具体的に言うと、
(1)最適な提案ができる
=ご相談をいただければ、
事故から「最適で最短」の解決策を提案できます。
「後遺障害等級がついてからまた相談に来て」、など最低な回答はしません。
(2)事故態様の確認
=物件事故か人身事故かというのは、大きな違いで、ここからチェックしていきます。
(3)整形外科の紹介
=相談・依頼時期、お住いの地域等によりますが、整形外科の紹介ができます。
(4)診断書の記載内容の確認
=「右手」が痺れているのに、”左手”と記載されていたりすることも稀にあり、
細かく記載をチェックいたします。
(5)症状固定日の正確な設定
=後遺障害等級認定を目指してる頚椎捻挫のご依頼者が5ヶ月で症状固定になったことに、なんの疑問も持たずに事案を進めません。←なんの疑問を持たない「交通事故に強い」、と謳う弁護士もいます。
(6)後遺障害診断書の記載内容の確認と加除修正依頼
=記載内容に気になる点があれば、医師に確認し、可能な限りで、加除修正依頼をいたします。
箇条書きですが、以上です。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
症状の連続性と一貫性の重要性
症状の連続性と一貫性は最重要です
自賠責保険は、
症状と通院の連続性と一貫性を重視しています。
具体的には、
交通事故後、
A病院→B整形外科→C整形外科という流れで通院をして、
C整形外科で症状固定を迎えたとします。
この時、C整形外科で「手の痺れ」が後遺障害診断時に残っていて、
後遺障害診断書にも記載されたものを用意して、
自賠責保険の被害者請求をしたとき、
「手の痺れ」の連続性・一貫性がポイントになります。
自賠責保険審査は厳しくみています
被害者請求後、
自賠責側からA病院・B整形外科・C整形外科に医療照会が入り、
上記、すべての医療機関で「手の痺れ」が、
”初診時から終診時まで”認められないと、
自賠責側は、「連続性・一貫性なし」と判断して、
後遺障害等級「非該当」の評価をしてくることがあります。
本当に厳格な審査だと感じます。
受傷後の実態と自賠責保険審査との大きな”溝”
交通事故後から「手の痺れ」が出現する人もいれば、
数日後に痺れを感じ始める人もいます。
この外傷性の怪我の実態と自賠責側の審査に、
大きな”溝”があるがために、
残存症状と後遺障害等級に整合性がとれない現実があります。
楽じゃありません。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
症状固定後も通院の継続を
自賠責保険上の後遺障害等級認定は、本当に難しいです。
初回申請で通ることもありますが、 通らないこともあります。
この時、症状固定後の通院を継続していることが、
異議申立で変更認定を勝ち取る大きなポイントです。
実際に、 最初の症状固定日から転院日まで数ヶ月空いたことを指摘され、
「非該当」の理由の一つとされた事案もありました。
症状固定に至るまでも苦労しますが、
症状固定を迎えてから全てが始まる、と考えてください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
後遺障害認定における医師の役割(交通事故・自賠責保険)
後遺障害認定は「医師」協力があってこそ
自賠責保険上の後遺障害等級認定を得るためには、
医師の協力は必須です。
したがって、
・医師と喧嘩した、
・患者側の自己主張が強すぎる、
・患者側の情緒が不安定、
・「受付や事務局に対する態度」と「医師に対する態度」が違う患者、
など他者と信頼関係が築けないような方は、
後遺障害等級認定は難しいと思ってください。
医療機関にお金を払っているのだから、などといった理由で、
自分本位になる患者は、医療機関が協力をしてくれません。
医師の役割は書面作成ではなく「治療行為」
医療行為や診断書作成を行うのは医師の仕事でありますが、
それは当たり前のことではありません。
医師法19条2項では、
診断書等の交付の求めに関しては拒否できない、のが原則です。
しかし、「正当な事由」がある場合には、
診断書等交付を拒否できる、ともされています。
医師法など法律を持ち出す前に、
人としてのわび・さびや礼節、誠実な態度をもって、
医師や受付と話し合いをすれば、
よっぽどのことがない限り、診断書交付を拒否されることはありません。
患者側にも問題があることがありますので、要注意です。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
後遺障害診断書を取得する方法
交通事故による怪我の治療開始後、
6ヶ月~1年経過したいずれかの時点で、
症状固定の判断を医師にもらい、
後遺障害診断書の作成を依頼することになります。
この時の注意点は、
(1)医師がいる医療機関での通院実績が定期的にあること
>接骨院に偏って通院をしている場合、医師が診断書の作成を拒否することがあります。
(2)健康保険又は労災保険を使っている場合
>自賠責書式診断書の作成を拒否されることがあります。
そのため、医療機関初診の際、自賠責書式の診断書作成に協力をしてもらえるか要確認です。
(3)医師や事務局の方に嫌われる態度をとっていないこと
>結論、診断書作成は、医師など医療機関関係者様の協力があってできることです。嫌われるような態度や横柄な態度の患者に、協力をしてくれる人はいないです。
後遺障害診断や後遺障害等級認定のためには、
医師の協力が必須です。
医師も仕事であるとはいえ、心ある人間であると僕は思います。
横柄な患者より、
素直で誠実な患者には前向きな協力をしてくれます。
この点、忘れてはいけません。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。