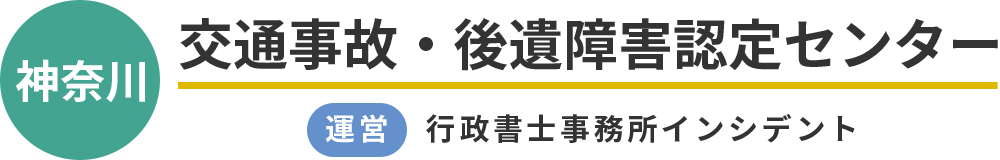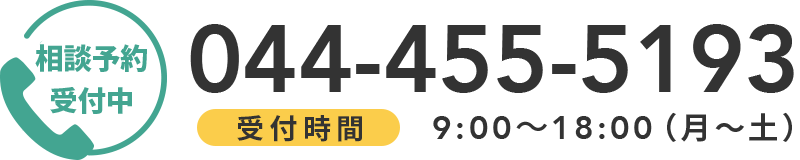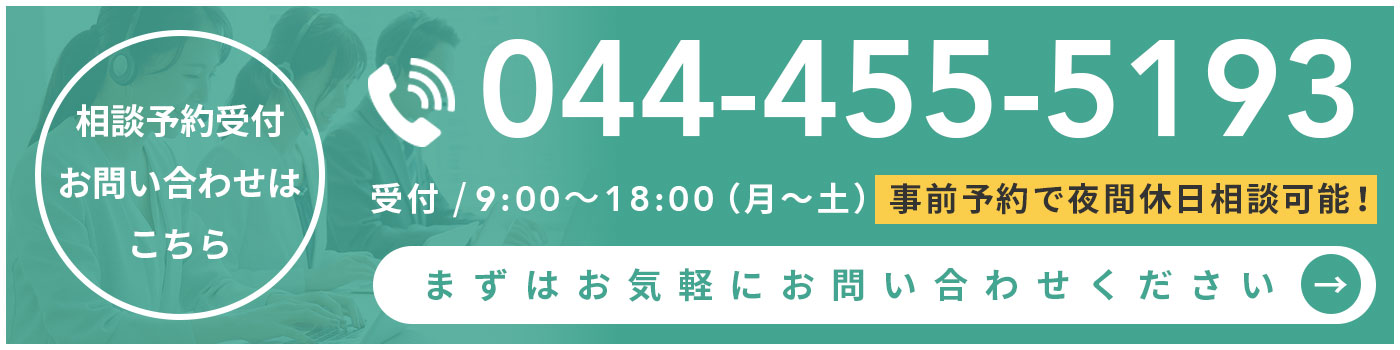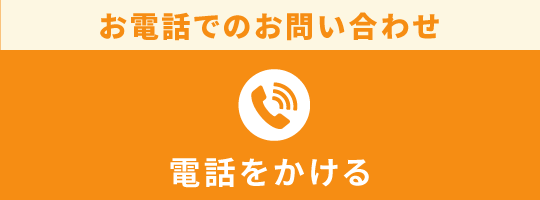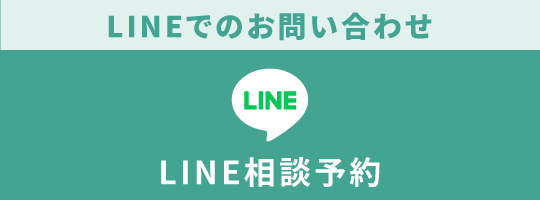このページの目次
1.関節系の後遺障害等級認定のための対策
交通事故による「関節系」の怪我はさまざまなものがありますが、
弊所ご依頼者で経験しているのは、
「肩関節」が多いです。
肩関節の怪我は、自転車やバイク乗車時に、自動車に衝突されたことにより、
・肩から地面に叩きつけられた、
・手で受け身をとったが耐えられなかった、
などの要因で肩関節の負傷につながったと考えられます。
肩関節の怪我は、鎖骨骨折や腱板損傷など種類がありますが、
交通事故直後は、手術対応になることもあります。
肩関節の後遺障害等級認定のための対策としては、
基本的に、頚椎捻挫(=むちうち)の場合と変わりはありません。
つまり、
(1)事故日(治療費開始日)から6ヶ月超の通院
(2)週3回の整形外科への診察・リハビリ
(3)主治医先生の協力を得る
の3点をクリアすることが、後遺障害等級認定を得るための土台です。
2.可動域検査値だけでは足りない
肩関節などの「関節系」の後遺障害等級としては、
A.機能障害(可動域制限)
B.変形障害
C.神経障害
D.非該当
の4つパターンが考えられます。
関節系の場合の後遺障害等級は、被害者も主治医先生も、
まずは「機能障害(=可動域制限)」で後遺障害等級の評価を得られるか否かを検討するように察しますが、実際は難しいところでもあります。
後遺障害診断書には、
関節の可動域検査値を記載する欄がありますが、
この可動域検査値が、認定条件を満たすだけの3/4以下または1/2以下の検査値の記載があっても、
それだけでは足りず、
可動域制限の原因となる画像所見が必要です。
酷な表現をすれば、自賠責保険の審査側の目線で考えると、
・可動域検査値はごまかせるだろう
↓
・だからこそ、骨がうまくついていない、変形しているなどの画像で判断をする、
となります。
3.関節系の後遺障害等級認定の進め方
先述したように、交通事故により肩関節(たとえば鎖骨骨折)の怪我を受傷した場合は、
手術対応になることがあります。
手術対応になれば、骨折部がつかない、変形して骨がつく、といったことはあまり起きにくいため、
機能障害(=可動域制限)で後遺障害等級認定を得ることは難しいと考えます。
したがって、肩関節の怪我であっても、
基本に忠実に、
6ヶ月の通院、週三回、整形外科への通院をクリアした上で、
まずは14級認定を確保するような進め方をするのが最善です。
ご相談者から「肩関節の怪我、鎖骨骨折、手術あり」と聞いて、
「12級や10級は認定されますよ」と安易な回答や案内をするような行政書士や弁護士もいらっしゃると思いますが、少々危ない回答です。
「どんな怪我でも認定される保証はなし」
「どんな怪我でも認定されない保証はなし」
ということを肝に銘じて、行政書士事務所インシデントでは、交通事故被害者のサポートをして参りたいと思います。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。