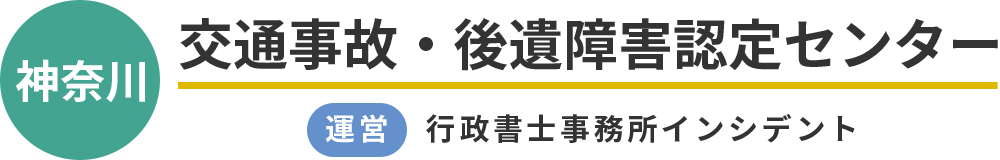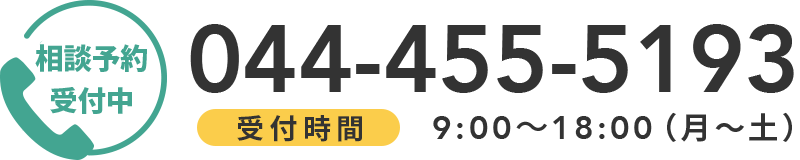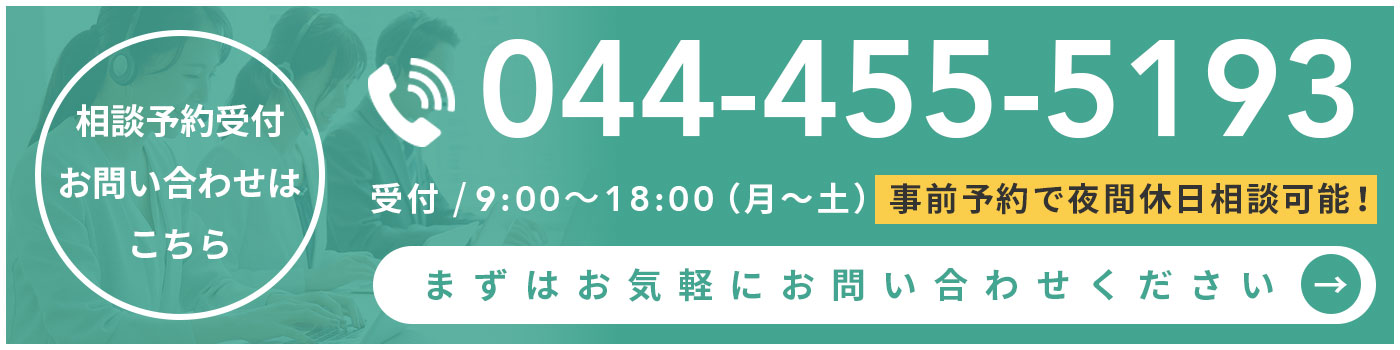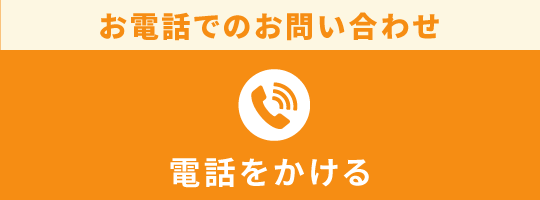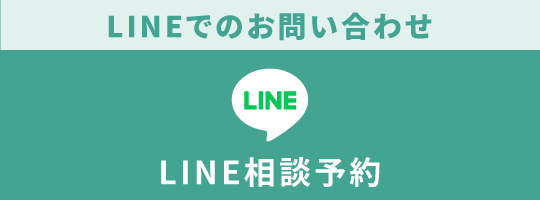むちうちの後遺障害申請について
画像所見と治療費の打ち切り(交通事故・自賠責保険)
交通事故対応が早い相手方損害保険会社は、
事故後レントゲンやMRIを撮影したタイミングで医師面談を実施し、
医療機関からレントゲン画像・MRI画像の資料などを取得する場合があります。
これは、今回の怪我が外傷性であるか否かの確認のためです。
頚椎・腰椎の椎間板の損傷は、
(A)外傷性でも、
(B)加齢性でも、
考えられるものです。
相手方損保会社側が、
加齢性による椎間板の損傷・変性と判断した場合は、
それを根拠に治療費の打ち切りの打診をしてくる可能性があります。
相手方損害保険会社の治療費打ち切り後の対策として、
健康保険または労災保険などに切り替えて治療を継続するか否か、
準備をしておくことをおススメいたします。
交通事故を原因とする自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。
行政書士事務所インシデント LINE公式
https://lin.ee/txFuVKY

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
追突事故はふとした瞬間に(交通事故・自賠責保険)
オートマの自動車が普及したことにより自動車の運転はとても楽になったように思います。
僕は、18歳のころ(2004年頃)にマニュアル車で自動車運転免許を取得いたしましたが、
いまは、身分証明書としてのみ使っています。
そもそも自動車の運転は嫌いで、心に大きなストレスがかかります。
さて、オートマ自動車が普及したことと同時に増えたのが、
「クリープ現象」による追突事故かと思います。
クリープ現象による追突の場合は、追突車両の時速としては、かなりの微動であるため、
・被追突車両の損傷、
・被追突車両の運転者・同乗者の怪我、
というのは軽微であると思われますが、事故は事故です。
交通事故後は、警察・損保会社などに報告をしてください。
その場で示談をすると、後日、被追突車の運転手等(被害者側)から、
治療費・慰謝料などを永遠と請求をされてしまう可能性はあります。
そして、クリープ現象による交通事故被害者でも、
自賠責保険上の後遺障害等級申請まで狙って、
弁護士基準で示談をしようとする人はいるでしょう。
これが交通事故の損害賠償の実態で現実です。
クリープ現象は、ふと気が抜けた、油断をした瞬間にブレーキから足が離れて、追突してしまいます。
要注意です。
交通事故を原因とする自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。
行政書士事務所インシデント LINE公式
https://lin.ee/hjT0zKB

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
治療費の打ち切りの流れ(交通事故・自賠責保険)
相手方損保会社からの治療費の打ち切りは、
(1)相手方損保会社⇒患者本人 又は 委任している人がいれば委任先(弁護士)
↓
(2)相手方損保会社⇒通院している医療機関に○○月末までの補償します
という流れで治療費の打ち切りの連絡が入ります。
ここで、患者が治療継続の希望があるのにも関わらず、
相手損保会社からの治療費打ち切りの連絡に対して、
委任先の弁護士が「はい。わかりました。」とただ了承をしてしまうようであれば、
その弁護士は頼りないです。
むしろ、患者本人が、相手方損保会社と調整して、
治療期間を引き延ばすことができるくらいに、
”弁護士より患者の方がうまく話ができる”というケースもあります。
相手損保会社の治療費打ち切りに対して、
弁護士であれば交渉をして、
治療費補償の期間を1ヶ月程度、延長させるぐらいは最低限やるべき仕事です。
はい。わかりました。じゃない。
本当に情けない。
交通事故を原因とする自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。
行政書士事務所インシデント LINE公式
https://lin.ee/qyVqhjc

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故慰謝料800万円増額?(交通事故・自賠責保険)
交通事故・むちうち・後遺障害についてのかなり長いランディングページをみましたが、
胡散臭いです。
自動車同士の追突事故の被害者が、
当初、頚椎捻挫の診断されていて、
相手損保会社からの示談金提示額が100万円だったところ・・・
弁護士に依頼した途端に、
・頚椎捻挫の診断から「頚椎損傷」になり、
・とても簡単に12級13号が認定され、
・100万円の相手方損保会社提示額から→950万円になった
という夢のような話です。
まず、自賠責保険会社は診断名の連続性・一貫性を重視するため、
事故日から6ヶ月経過後に「頚椎損傷」の診断名がつき、
それをもとに後遺障害等級申請をした場合の結果通知書には、
「頚椎損傷の診断名は、事故から6ヶ月を経過した後に診断されたものであり・・・」という理由で、
本件事故の関係性は否定される可能性が高いです。
頚椎損傷という診断名もあいまいです。
「頚髄」損傷や「脊髄」損傷はよく目にしますが、頚椎損傷という診断名は稀な診断名であります。
また、このランディングページの主人公の交通事故の症状が、首の痛みのみのようです。
仮に「頚椎損傷」だとしても、頚椎損傷を起こした場合は、
首の痛みに加えて、腕や手に神経症状が出現するのが典型です。
そして、首の痛みのみで12級13号が認定されるというのも、
あまりにも、うま過ぎな話ですし、誇張ともとれる表現に感じます。
12級13号の認定に至るようなレントゲン画像やMRI画像の紹介もなく、根拠が薄弱です。
まとめるとこの広告は、
(1)頚椎捻挫が6ヶ月経過後でも頚椎損傷に容易に診断名の変更が可能で、
(2)首の痛みだけでも12級が認定され、
(3)特にレントゲン所見・MRI所見など画像所見なしでも12級認定される、
というストーリーのため、閲覧者が勘違いする広告となっています。
実際は、こんなにうまい話はありません。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
後遺障害認定率が低い理由(交通事故・自賠責保険)
自賠責保険の後遺障害認定率は「5%」
自賠責保険の後遺障害等級認定率が低い理由としては、
「通院面のハードルが高い」ということに尽きます。
弊所で多くお手伝いしている頚椎捻挫(=むちうち)に関しては、
(1)事故日から6ヶ月超の通院期間が必要
(2)週3回以上の通院が必要
(3)整形外科などの医療機関への通院が必要
という「後遺障害等級認定のための土台3点」をクリアしなければなりません。
時間的余裕がある人が後遺障害認定を勝ち取る
弊所にいらっしゃる相談者のなかには、
上記、後遺障害等級認定のための土台3点を相談時にお話すると、
当初の「絶対後遺障害等級認定を勝ち取るんだ!!」という気迫がなくなってしまう方も多いです。
わかりやすく言えば、弊所のむちうちのご依頼者で、
後遺障害等級認定を勝ち取った方の傾向としては、
(A)経営者・自営業者
(B)専業主婦
(C)お子様
など、時間と経済的に、余裕があるかたが多いのも特徴です。
会社に勤務にしてたら通院できない
一般的な会社員の勤務時間はいわゆる「9時6時(9時~18時)」です。
整形外科の開院時間もそれと似ており、ここに12時から15時までは昼休憩となるため、
会社員は、昼休みにパッとリハビリを受診することさえできません。
そのため、営業時間が柔軟な、整骨院への通院がメインとなってしまい、
後遺障害等級認定のための土台が作ることができない状況となってしまいます。
相談者の中には、
・こんなに症状がつらい
・MRIにヘルニアがあると言われた
など医学的な認定要素が揃っている相談者もおり、
そんな相談者が後遺障害等級認定されない理由は、
この「後遺障害等級認定のための土台3点」をクリアしていないことが多いです。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故後の貧血?(自賠責保険・後遺障害)
交通事故による頚椎捻挫(むちうち)を受傷した場合、
「貧血」のような症状が出現することもあるようです。
この場合、貧血の症状が気になるようであれば、
まずは一般内科を受診してもよいと思いますが、
内服薬服用による悪化等をしないよう気を付けなければなりません。
理由としては、自賠責保険上の後遺障害等級審査は、
あくまで頚椎捻挫を基礎に審査をするため、
”交通事故外傷による整形外科的な怪我による症状ではなく、
精神的な要因による症状の継続や悪化と判断されてしまう”のは、
自賠責保険審査上は不利に働くように感じます。
交通事故による怪我の場合、
・相手方の存在や態度
・相手方損保会社の圧力
・相手方への処罰感情
・どういった解決に至るのかという不安
など複雑な状況になりがちです。
交通事故に関すること以外に、仕事や日常生活になにかしら不安があり、
症状が複数・複雑に感じられるのかもしれません。
どんなに辛くても、
ゆっくり鼻から息を吸い、静かに吐き、深い呼吸を忘れないようにしてください。
交通事故を原因とする自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。
行政書士事務所インシデント LINE公式
https://lin.ee/T3M8hoU

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
むちうちと症状固定(交通事故・後遺障害)
交通事故によるむちうちを受傷し、
相手方損保会社から「4ヶ月程度で症状固定の連絡がきました」、
という相談を受けることがあります。
まず、損害保険会社は症状固定の判断はできません。
損害保険会社ができる判断は「任意一括対応の打ち切り(=治療費打ち切り)」です。
そして、損害保険会社の治療費打ち切りは、症状固定ではありません。
したがって、被害者が、自賠責保険上の後遺障害等級申請・認定を目指すのあれば、
(A)労災保険
または
(B)健康保険
に切り替えて、事故日から6ヶ月超通院をした上で、
主治医先生に症状固定の判断をもらい、そして後遺障害診断書の発行をしてもらい、
それをもって、自賠責保険に被害者請求をすべきだと思います。
むちうち(=頚椎捻挫)で、自賠責保険上の後遺障害等級認定を受けるためには、
事故日から6ヶ月超の治療期間がなければ、認定評価をされることはほぼありません。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
症状の根拠(交通事故・後遺障害)
交通事故によるむち打ち受傷後、
・頭痛
・腕や手の痺れ
が出現することがあります。
これらの症状に対して、
頭痛=脳神経外科
腕や手の痺れ=頚椎部のMRI撮影
とセカンドオピニオンや精密検査を受診することもあります。
この精密検査を受診しても、頭痛や腕や手の痺れの根拠が判明しないことはあります。
だからとって、自賠責保険上の後遺障害等級認定がなくなる、というわけではありません。
一喜一憂せずに、
(1)6ヶ月超の通院
(2)週3回程度の定期通院
(3)主治医先生との信頼関係構築
を意識して一歩一歩進めていけば、12級認定は難しくとも14級認定は引き寄せることはできます。
症状のすべてが、原因究明できるわけではないように考えます。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
後遺障害 行政書士 神奈川県(交通事故案件)
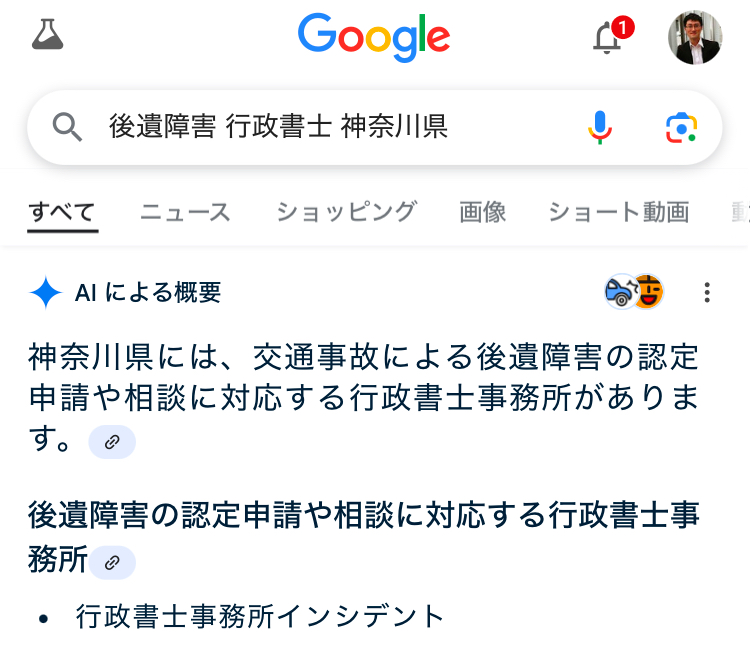
行政書士事務所インシデントのホームページの標準検索順位は、
「後遺障害 行政書士」に加えて、
「神奈川県」までネット検索にかけるとAIのおかげもあって、
弊所のホームページが上位にあがってきます。
地域名として神奈川県を入力するとネット検索上は、
高い確率で上位表示になります。
ちなみに、神奈川県を「川崎市」とかえると、
弊所一択の検索表示です。
弊所が、神奈川県や川崎市など地域名までこだわるのは、
医師面談や出張サービスを強みにしているからです。
このご時世、リモートワーク、zoom面談が流行っていますが、
結局、直接会った方が効率的だった、ということは多いです。
そして、直接顔を見せたり、会いに行ったりする方が、
人間というのは愛着がわくものです。
聞いた話ですが、
とある弁護士なんかは、
「あの診断書の、ここを、こう修正してください」などと、
医療機関事務局・院長先生に、電話をしてくるだけの対応のようで、
「偉そうだな」といつも感じます。
弊所は、ご依頼者の都合の良い場所に出向くスタイルでやっておりますので、
関東圏、主に神奈川県、東京都、千葉県・埼玉県の一部と対応地域を限っております。
したがって、
東北や甲信越、関西、
意外にも福岡からの問い合わせも多いですが、
依頼を受けられないので問い合わせをしないで欲しいです。
関東圏のかたは、ぜひ「後遺障害 行政書士 神奈川県」でネット検索して、
弊所までお問い合わせください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
弁護士特約の注意点(交通事故・自賠責保険)
弁護士特約をつかって弁護士に依頼をしやすくなっています。
○○しやすいというのは注意をしなければなりません。
安ければいいというものではありません。
被害者自身の負担がないから相談をしやすい、依頼をしやすくなっていますが、
弁護士のこと、交通事故後どんな対応を弁護士がしてくれるか、
今後のリスク(=治療費打ち切りの可能性など)を弁護士からご相談者に伝えないで、
また、ご相談者も質問や疑問を持たずに、
委任状だけ交わしてしまうケースもあるようです。
弁護士は、弁護士特約から着手金入金後はなにもしない・できない、という事例もみます。
交通事故業務ができない弁護士もたくさんいるから、
気を付けてください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。