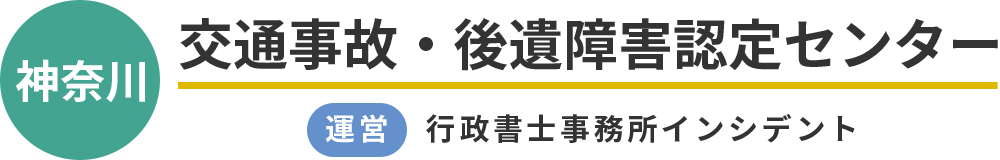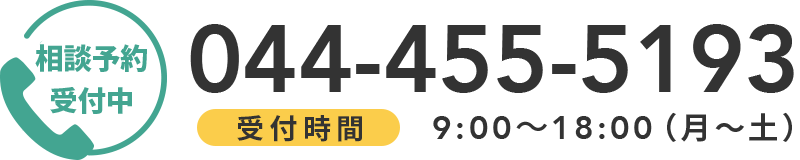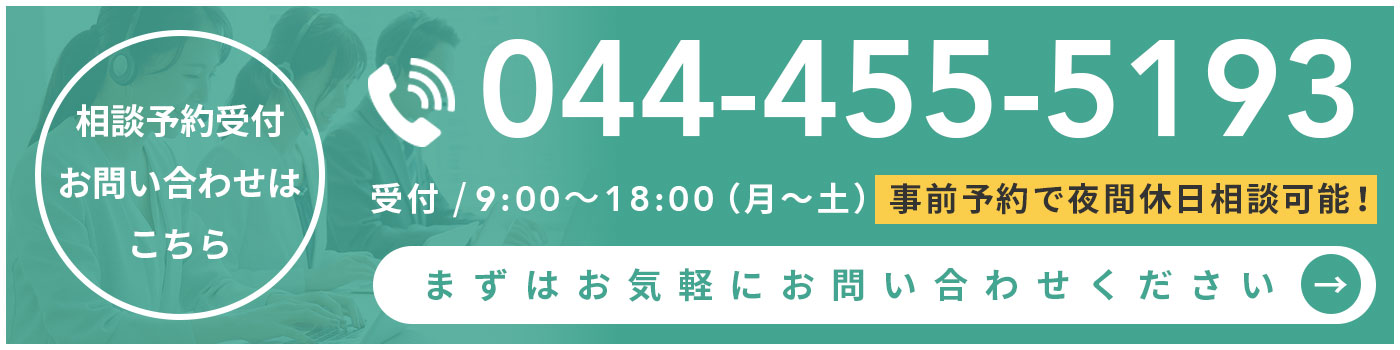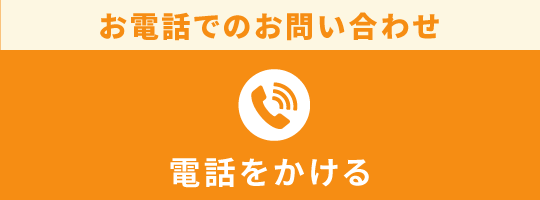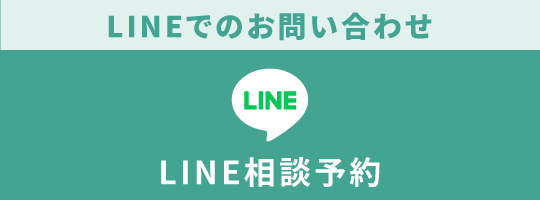むちうちの後遺障害申請について
時間がかかる…自賠責保険の後遺障害等級認定
先日、弊所ご依頼者の自賠責保険上の後遺障害等級14級認定が確定いたしました。
申請から結果通知まで約2ヶ月。
毎年のように審査に時間を要している感覚です。
また、自賠責保険上の後遺障害等級が認定された場合は、
(1)自賠責保険金額の入金
↓
(2)後遺障害等級票など書類で結果通知
という流れです。
つまり、(2)の書類が先に届いた場合は、
「非該当」の可能性が高い、ということです。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
お近くの交通事故専門家に相談してください
弊所は関東在住の方からのご依頼をお待ちしております
弊所には、意外なほどに関東以外の方からのお問い合わせをいただきます。
ご相談者曰く、インターネット検索をした際、
弊所のホームページが一番にあがってきたから相談をしてみました、
というありがたい言葉をいただきます。
地道にコラム更新をした成果でしょうか。
全国からお問い合わせいただくのはありがたいですが、
関東以外の方の依頼をお受けするとなると、
弊所報酬はその分高くなります。
そのため、基本、ご依頼をお受けすることはありません。
インターネットやホームページ広告の効力は絶大で、本当にありがたいですが、
弊所に電話問い合わせや相談をする前に、
弊所の「対応地域」をご確認をしてください。
ホームページでは検索しにくいページ構成になっているかもしれませんので、
以下、弊所の対応地域をご案内いたします。
弊所の主な対応エリア
川崎市
川崎区・幸区・中原区・高津区・多摩区・宮前区・麻生区
横浜市
鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ケ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区
相模原市
緑区・中央区・南区
東京都
港区・豊島区・板橋区・練馬区・世田谷区・大田区・町田市、立川市、武蔵野市
埼玉県さいたま市
西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区
が主な対応エリアです。
少々、限定的ですが、
上記、エリアは、弊所から整形外科等の紹介が可能なエリアのため闘いやすく、
ご依頼者の通院先のご紹介から価値提供をできると考えております。
ご案内したエリア以外でも、
関東であれば、積極的にお受けする所存ですので、
関東にお住いで、交通事故によるお怪我の症状で困っている方は、
行政書士事務所インシデントまでご相談ください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
「ぜったい」はない、後遺障害等級認定(交通事故・自賠責保険)
「絶対勝てる」、「絶対認定」をアピールする人は要注意
自賠責保険上の後遺障害等級認定は、
行政書士・弁護士が請求をかけても、
「ぜったい」認定という保証がありません。
もし、「絶対の認定保証」があれば、
弊所も、
(1)着手金0円で受任して、
(2)完全成功報酬
の報酬体系でお手伝いしたいな、と思います。
完全成功報酬制は危険
弊所の方針ですが、完全成功報酬制は採用しません。
理由としては、
(1)万が一、辞任した・解任された場合、0円労働となる
(2)キャラクターが強いお客様が増えがちになる(着手金0円だからお客様側にリスクないし・・・)
(3)自信のなさの裏返し
→「0円でやってあげているから失敗しても文句言わないでね」と言っているようなものです。
の3点です。
そう、やっぱり、お客様からお金をいただいたほうが、
責任感と緊張感が生まれ、仕事の精度や活力も高まると考えます。
弊所はしっかり報酬をいただきます。
弊所は、
・インターネットからのお客様
・ご紹介のお客様
どちらも問わず、原則、弊所の正規の報酬をいただきます。
ただ、お客様の諸事情や人柄を拝見しまして、
報酬をお下げすることはあります。
まずは、行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。
※一方、以下のコラムに記載した「センスのないご相談者」は、
弊所にお問い合わせも相談もしないでください。
よろしくお願いいたします。
タイトル「選ぶ責任、選ばれる責任」
https://asoffice-inc.com/column20240710/

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故のご相談は、じゅうぶんな聴き取りが大事(自賠責保険・後遺障害等級)
相談者の話を聴け
あたりまえのことですが、
初回電話相談時、
ご依頼前の面談時、
受任後の相談時、何気ない会話、
など、ご依頼者の話は丁寧に聴くこと、
わかったふりをせず、気になったことは質問をすること、
を心がけています。
具体的には、
交通事故業務の場合の初回相談時は、
・事故状況、
・事故後に最初に感じた症状、
・警察への届け出の有無、人身事故か物件事故扱いか、
・過去の事故の有無、
・過去に後遺障害等級認定を受けたことがあるか否か、
などを丁寧にお聴きし、その回答から案件の方針が決まっていきます。
目先の着手金より大切なこと
例えば、
過去に事故の経験があり、むちうち(頚椎捻挫)で後遺障害等級認定の経験がある場合に、
今回事故ではむちうちと他に腰椎捻挫を受傷した場合は、
むちうちでの後遺障害等級認定は捨てて、
腰椎捻挫に絞って闘った方が可能性としては高くなりますし、広げることができます。
この時、目先の着手金に目がくらんだり、
過去の事故等の聴き取りが甘くなると、
案件の進め方が全く違ったものになり、
むちうちだけに集中して後遺障害等級14級の認定を受けても、
過去の14級と重複して、自賠責保険金額を受領できず、
ご依頼者に不利益と余計な時間・労力をかけさせてしまうことになります。
→意外とこういう事例は多いです。
依頼を受ける側(行政書士・弁護士)が、ご相談者や交通事故問題に実は無頓着で、
「弁護士特約はしっかり払ってくれるのかな?」ということばかりに、
興味がいってしまう方によくあらわれる現象です。
断ることも相談者側の利益
こういった丁寧な聴き取りから、
弊所で受任すべきではないと考えた場合は、
依頼をお断りすることもあります。
これは、着手金が高い・低いとかそういう目先のお金の問題ではなく、
明らかに勝ち目がないと感じた場合、
依頼を受けないことがご相談者にとって最高の経済的利益となりうるものです。
特に、
・事故から数年経過していて、本件事故による怪我の症状か不明である、
・事故からろくに通院をしていない、
・初回申請「非該当」。異議申立申請を希望しているが、症状固定後、通院をやめている、
などの事情がある場合は、ご相談者に丁寧に説明をし、
それでも闘う、という気持ちが強い方以外はお断りしないと、
後々のクレームの種になります。
断る勇気。これも時には大切です。
交通事故を原因とする自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。
行政書士事務所インシデント LINE公式
https://lin.ee/glBTxPB

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故は、はじめてのことばかり
交通事故は人生に一度遭うか、遭わないか、というほどに稀なトラブルです。
そのため、交通事故に遭った後は、
初めてのことばかりだと思います。
交通事故後のはじめておこなう対応
本コラムでは、交通事故の「被害者側」にたって、
交通事故後に対応すべきことをご案内いたします。
(1)交通事故発生後:警察への届け出
(2)警察の実況見分
(3)相手方の情報の取得
(4)相手方損保会社への事故報告をしてもらう
(5)被害者自身加入の損保会社への事故報告
(6)救急者に乗るか否か、乗った場合は大きな医療機関での診察や検査の受診
(7)家族や職場などへの報告
などなど、箇条書きにしただけでも、たくさんのやるべきこと、やらないといけないことがあります。
交通事故翌日以降からはじめておこなう対応
(1)救急搬送された場合、その後の通院は自宅など通いやすい整形外科等へ通院するため紹介状の取得
(2)通院しやすい医療機関を見つける
(3)整形外科に通うか・整骨院に通うかの選択
(4)家族や職場が交通事故後の症状を理解してくれるか否か
(5)通院をすることの重要性について家族や職場の理解
(6)相手方損保会社からの連絡の対応、同意書など書類の作成・返送
(7)いつまで、どのくらい通院するのが最善なのか
(8)症状が治っていないのに、治療はだいたい3ヶ月を目途に終了?
(9)症状固定って?後遺障害診断って?
(10)通院や業務中の事故の場合は、労災関連書類の取得や作成
などなど、交通事故翌日以降から相手方損保会社や医師などから、
よくわからないことを言われて、正しいのかよくわからないまま進んでいく不安があると思います。
交通事故後どうしたらわからない、は行政書士事務所インシデントに相談してください
初めての交通事故、
その交通事故後の対応の仕方で悩んだり、
交通事故後の怪我の症状や後遺障害申請で不安を抱えている人は、ぜひ弊所までご相談ください。
交通事故の状況、その後の流れ、希望する解決などは、十人十色です。
弊所では、ご相談者ごとに、最善の提案や解決策をご案内いたします。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
相応しい後遺障害等級認定のために(交通事故・自賠責保険)
症状が改善しない場合は後遺障害等級申請をしましょう
交通事故による怪我の症状が、
治療をしても残存している場合は、
自賠責保険上の後遺障害等級申請をすべきと考えます。
この自賠責保険上の後遺障害等級申請の流れは、
(1)主治医先生の症状固定の判断
(2)主治医先生の自賠責保険書式の後遺障害診断書作成
(3)相手方自賠責保険会社に書類一式送付
(4)自賠責損害調査事務所の損害調査・認定判断
となります。
自賠責保険は「書面審査」
この自賠責保険の後遺障害等級審査は、
原則「書面審査」です。
顔が見えない、実際の診察もない、
診断書を基礎とした書面のみの審査のため、提出する書類や資料には、
慎重に慎重を重ねなければなりません。
実際の怪我の症状に相応しい後遺障害等級評価を受けにくい
自賠責保険は「書面審査」であるがゆえに、被害者の症状に見合った後遺障害等級認定とならないこともあります。
一方、労災保険の後遺障害等級審査は、
労災書式の後遺障害診断書を労基署に提出後、
労災保険の顧問医による診察が実施されるため、
被害者の怪我の状態や症状と整合性のある後遺障害等級が認定されやすいと考えます。
そのため、自賠責保険の後遺障害等級と労災保険の後遺障害等級が一致しないことがあります。
具体的には、頚椎捻挫(むちうち)のケースで、
自賠責保険=14級9号認定
労災保険=12級13号認定
というケースは少なからずあります。
14級認定は尊い価値(=勝ち)
2024年7月現在、
頚椎捻挫(むちうち)で自賠責保険上の後遺障害等級認定を得ることは本当に難しくなりつつあります。
自賠責保険の後遺障害等級評価と労災保険の評価に乖離があるとしても、
自賠責保険上の後遺障害等級「非該当」と「14級」は天と地ほどの差があります。
したがって、弊所の方針は、まず「14級確保」の闘い方をご依頼者に提案し、
最低限の着地点・価値をご提供することに集中して取り組んでおります。
交通事故・自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。
行政書士事務所インシデント LINE公式
https://lin.ee/fo5ZssN

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
選ぶ責任、選ばれる責任(交通事故・自賠責保険)
交通事故被害者が、
インターネット検索や誰かの紹介で、
弁護士や行政書士への相談や依頼をする場合、
選ぶ側(=相談する側)
選ばれる側(=相談・依頼を受ける側)
にそれぞれ責任があると思います。
選ぶ側(=相談する側)の責任
弊所が、選ぶ側(=相談する側)にセンスがないな、と感じる瞬間は、
電話問い合わせについては、
・無料だと思い込んでいる(弊所は有料相談・有料依頼のみの対応)
・非通知でかけてくる
・匿名希望で情報だけを聞き出そうとする
・こちらの質問に対して、結論を答えず、その前置きや結論の周辺情報の回答が多い
・すでに弁護士に依頼しているのに、「これはどうなんですか?」という質問
>弁護士に聞いてください
・弁護士等に依頼をしていながら、後遺障害等級申請をした後に、、「これって認定されますか?」という質問
上記が弊所がすぐに思いつく、センスがない相談者です。
そして、
・「交通事故専門」の謳い文句
や
・弁護士特約があることの気安さから、
複数の弁護者や行政書士に相談をせずに、勢いで依頼をしてしまった後に、
後悔をする方もいらっしゃいます。
弁護士特約があるのであれば、それを活用して、
いろんな弁護士・行政書士の見解や仕事の姿勢を見た上で、依頼を決めてもよいと思います。
選ばれる側(=相談・依頼を受ける側)の責任
たくさんの中の法人や事務所の中から、
ご相談者が選んで、相談なり、依頼をしてくれたなら、
選ばれる側は、真剣に取り組みましょう。
「とにかくたくさん通院してください」、
では、なんでたくさん通院する必要があるのか、がわからないわけで、
「症状固定になったら教えてください」
では、いつ症状固定にしていいかわからないし、わからないから依頼しているわけで、
「いまは、後遺障害等級がないため、等級が決まってからまた相談してください」
では、勇気をもって相談した意味がないし、その等級認定を勝ち取りたいから相談をしているわけです。
選ばれる側に、センスがない対応事例もたくさん見受けられます。
交通事故専門を謳う事務所の中には、疑わしいものもあります。
弁護士特約から着手金をもらえればそれでよい、という事務所もあります。
行政書士事務所インシデントは本気です
弊所は、極論すると、
「交通事故業務しかやらない」と決めて創業をいたしました。
つまり、すべてを捨てて、交通事故業務一本で走り出したので、
気合や思い入れが他社とは全く違います。
この気合が空回りして、依頼者との方針の違いで、解任されてしまうことは正直あります。
しかし、依頼者の状況を1㎜でも、1歩でも前進させようという思い、
前のめりで闘おうとした姿勢に嘘偽りはありません。
A.依頼した後、なんの音沙汰もなくなる事務所
と
B.依頼した後、積極的に連絡が来たり、今後はこうしましょう、と提案してくれる事務所
あなたはどちらを選びますか?
交通事故を原因とする自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。
行政書士事務所インシデント LINE公式
https://lin.ee/hjT0zKB

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
どういう流れなのか~交通事故賠償~
示談解決までの4つの山場
結局、交通事故賠償請求はどういう流れなのか?
この点、把握していない被害者も多くいらっしゃるように考えます。
簡潔にご案内しますと、
交通事故賠償の解決までは、山場が4つあります。
(1)交通事故発生
(2)警察・損害保険会社などへ事故の届出
(3)治療開始:(山場1:どこの整形外科に通うか?
(4)症状固定(山場2:いつ症状固定にするか?)
(5)自賠責保険後遺障害等級申請・認定(山場3:等級認定を得られるか?)
(6)示談等解決(山場4)
となります。
行政書士が担う重要な役割
弊所が考えるポイントは、(3)から(5)となります。
そして、弊所が専門的にかつ適切にお手伝いできるのは、
(3)治療開始:通院先選定
>どこの整形外科に通うかがとても重要で、弊所から整形外科のご紹介も可能な場合もあります。
(4)症状固定
>適切な症状固定日の設定を弊所でご提案いたします。
※交通事故専門を謳う弁護士・経験豊富な医師でも症状固定日の設定を間違うことがありますので、要注意です。
(5)自賠責保険後遺障害等級申請・認定
>主治医先生と相談・協力の上、後遺障害等級認定の可能性を高める後遺障害診断書の取得をサポートいたします。
遠回りしないためにも、まずは弊所にご相談ください
上記のように、行政書士である弊所は、
良き解決になるか否か、とても重要な役割を担います。
この重要なポイントについて、
意識して、そして、集中して取り組むのが、行政書士事務所インシデントです。
この重要な部分の綿密なサポートをなくして、
最短・最適な解決は望めません。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故で困っているご相談者のために、ちゃんとした仕事をしましょう(自賠責保険・後遺障害等級)
依頼を受けたらマジでやりましょう
当たり前ですが、
ご依頼者からお金をいただいたのであれば、
ちゃんとした仕事をしましょう。
重ねて案内いたしますが、
交通事故分野には、幸か不幸か、
「弁護士特約」というものがあります。
弁護士特約の功罪
この弁護士特約があれば、
ご依頼者(被害者)の報酬負担がないため、
依頼をしやすいことになっていますが、
これが仇となることがあります。
自分(相談者・依頼者側)の報酬負担がないため、
依頼する際の慎重さに欠け、
・東京都や神奈川県の弁護士だし
・インターネットに検索で出てくる有名?ちゃんとした?弁護士だし
・そもそも弁護士だし
というのなんだかわからない選択基準によって、依頼をするケースもあるように思います。
しかし、依頼後は、なんの音沙汰も進捗の連絡もない。
連絡があったかと思えば、
「相手損保会社から治療費を打ち切られましたので、今後は健康保険切替で治療をお願いします」、
となんの脈絡もない突然の報告。
いまの弁護士に不満なら行政書士事務所インシデントに相談ください
ご依頼者は、治療費を打ち切られないよう、弁護士に依頼をしているところもあり、
相手方損保会社の言いなりであれば、依頼をした意味がないと思いませんか?
こういった事案は、意外にも多く、
この弁護士の仕事をしない姿勢や対応の不信感から、
弁護士を解任し、
弊所に乗り換えて依頼をされるご依頼者もいらっしゃいます。
このような事案でも、弊所は積極にお受けし、
弊所が連携している弁護士とチームで闘います。
弊所の理想的な体制は、
「後遺障害等級申請サポートは行政書士」、
「交渉サポートは弁護士」、
であり、実際、この体制で、ご依頼者に安心や適切な賠償金など「価値」を提供すべく闘います。
交通事故を原因とする自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。
行政書士事務所インシデント LINE公式
https://lin.ee/glBTxPB

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故の後遺障害認定歴は「ばれない」ことはない(自賠責保険)
過去の後遺障害等級認定は記録に残ります
過去に、自賠責保険上の後遺障害申請をしたことがあり、
さらには後遺障害等級認定歴がある場合、
自賠責損害調査事務所など、自賠責側に記録が残ります。
10年以上前は簡単に後遺障害等級認定が得られていたと感じます
例えば、頚椎捻挫の場合ですと、
10年以上前に頚椎捻挫由来の「頚部痛」で後遺障害等級認定歴がある場合に、
今回事故の頚椎捻挫由来の「頚部痛」を基礎に後遺障害等級申請、
この申請後に自賠責側から届く、後遺障害等級認定票には、
「~~~○○年○○月○○日発生事故受傷に伴う頚椎捻挫後の「頚部痛」の症状について、
14級9号の認定がなされており ~~~ 非該当と判断します」
という言葉は、提携引用文として、非該当の認定票には記載されます。
自賠責側にはちゃんと記録が残っています。
10年以上前の事故の後遺障害等級認定歴を持ち出して、
「非該当」の判断となりますので、
以前のように、簡単に?後遺障害等級認定を得られると思ったら、大間違いです。
同一部位でも”新しい症状”は認定の対象になります
しかしながら、過去と今回事故とで同一部位の受傷であっても、
今回事故で初めて出現した症状であれば、
後遺障害等級の認定対象となりますので、
簡単にあきらめず、弊所にご相談をいただければ幸いです。
交通事故を原因とする自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。
行政書士事務所インシデント LINE公式
https://lin.ee/cSD1z48

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。