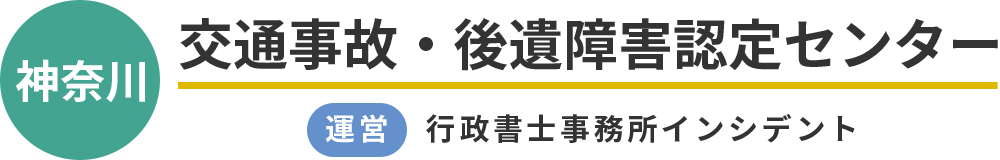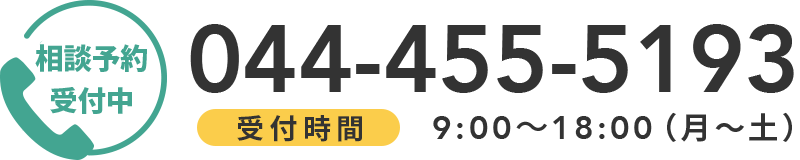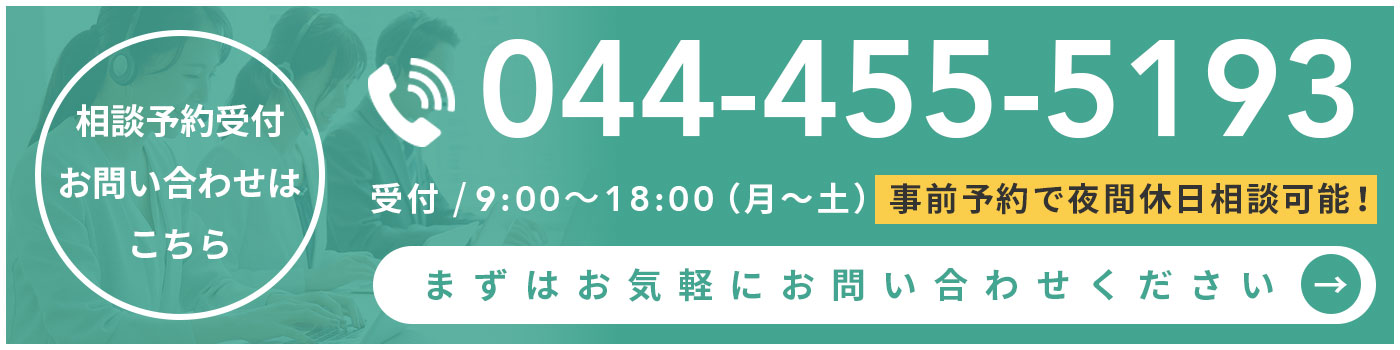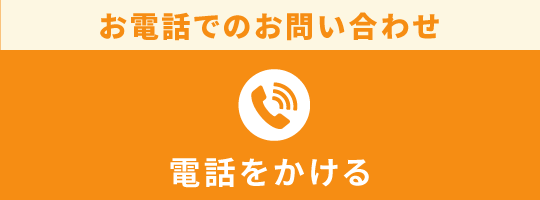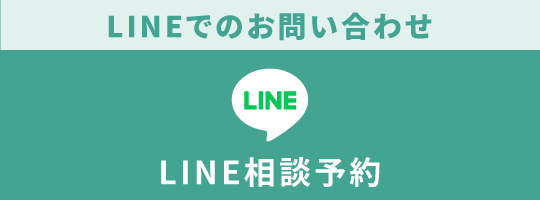自賠責保険制度について
自賠責保険の通院慰謝料の計算(交通事故・損害賠償)
通院期間=3ヶ月
実通院日数=50日
の場合で考えます。
まずは、通院一日の慰謝料金額が4300円となります。
そして、4300円に「かける日数」としては、
(A)通院期間3ヶ月の場合は、30日×3=90日
(B)実通院日数には実通院日数に「2」を掛け算いたします。
本事例では、50日×2、つまり100日となります。
通院期間90日
と
実通院日数×2=100日
の少ない方を採用します。
結論、4300日×90日=38万7000円となります。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
症状固定日に注意してください(交通事故・自賠責保険)
ヤフー知恵袋の回答内容をみていると明らかに間違った回答もあります。
例えば、大腿骨骨折の症状固定日はいつにすべきか?という投稿に対して、
「医師が事故日から6ヶ月未満で症状固定としたのであれば、申請して良い」、
という回答をしていましたが、ぞっとしました。
たしかに、
事故日から6ヶ月未満でも症状固定にはできます。
6ヶ月未満の症状固定日で作成された後遺障害診断書をもって申請もできます。
ただ、ほぼ間違いなく後遺障害等級の「認定」とはなりません。
6ヶ月未満で症状固定にして、申請して、後遺障害等級を認定を得られるのは、
上肢または下肢の「切断」です。
「申請ができる」 と ”認定される”、
は全く別のものです。
ヤフー知恵袋の回答内容は、SNSと同等に、間違った回答も多くあります。
注意してください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
休業損害を請求する場合(交通事故・自賠責保険)
休業損害を請求する場合は、
休業損害証明書に加えて、
(A)会社員であれば「事故前年度の源泉徴収票」など
(B)主夫・主婦であれば「住民票」
(C)自営業であれば「事故前年度の確定申告書」
の添付が必要です。
ご依頼者への案内時には休業損害証明書だけなく、
添付資料までご案内し、送付をしてもらいましょう。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
政府保障事業(交通事故・ひき逃げ)
(A)交通事故の相手方自動車の自賠責保険が使えない(自賠責無保険車)
や
(B)ひき逃げなどで加害者が不明
の場合は、政府保障事業という制度があります。
お確かめください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
ヤフー知恵袋ベストアンサー(交通事故相談)
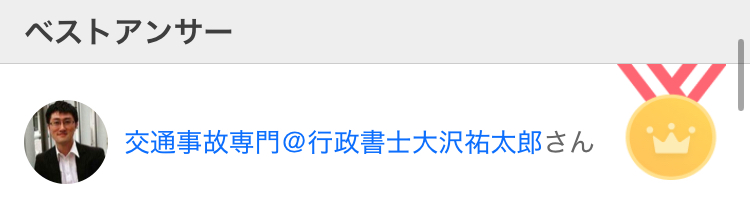
昨日1月7日は、ヤフー知恵袋の質問に対して回答をしたところ、
2件ベストアンサーをいただきました。
交通事故後の対応、
自賠責保険のつかい方、
など、交通事故対応についてわからないかたは多くいらっしゃいます。
他の回答をみていると、中には、その回答内容だったら、回答をしなくてもよいのでは?
と思う回答者もいます。
だからこそ、僕の詳細な回答が目立つ・際立つように感じます。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
弊所だからこそ、できることがある(交通事故・自賠責保険)
2025年も変わらず頼りない弁護士が多いですね。
(A)相手方任意保険未加入
(B)被害者が弁護士特約未加入
(C)後遺障害等級認定が未定
上記のような事案だといい顔をしない弁護士がいるようです。
情けないですね。
弊所は、
(A)相手方任意保険未加入でも自賠責保険の被害者請求を活用して、最大限の補償を受けてもらえるようサポートできます
(B)弁護士特約未加入でもご依頼者自身に行政書士報酬をいただければサポートできます
(C)後遺障害等級認定が未定だからこそ、後遺障害等級認定を得られるようにサポートできます
交通事故後、なにがなんだかわからないから、
頼りになりそうな弁護士に相談しているのに、
「症状固定を迎えてからまた相談してください」でご相談者を追い返すなんてひどいです。
むしろ、その症状固定を迎えるまでにやるべきことがたくさんあるわけですから、
交通事故分野を扱う士業としては情けない対応です。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
一文字・一行を確認することが重要(交通事故・後遺障害等級)
後遺障害等級申請を流れ作業にしてはいけない
弁護士に依頼をしているにも関わらず、
書類だけ預かって、なんのチェックもせずに、自賠責保険申請をしているようなケースもあります。
初回申請・非該当となった、
弁護士申請の自賠責保険請求書類を拝見すると、
後遺障害診断書には、
「○○を認めない」などの所見の記載がありながらも、
主治医先生に確認や修正依頼をしなかったのはどういうことでしょうか。
ご依頼者に代わって聞く、
ご依頼者に代わって嫌われる、
そういった役目が士業にはあると思いませんか?
右から左に書類を流すだけの某法人の業務遂行にはレベルの低さを感じます。
たくさん受任することが美徳ではない
その割には、SNS上では、交通事故専門家として、
「交通事故問い合わせ件数に対して受任率は・・・」などと投稿をしていて、本末転倒です。
受任率を上げて、顧客を増やす努力より、目の前の一件・一人を大切にすべきだと思います。
士業ビジネスの肥大化の弊害です。
従業員が多くても、お客さんが多くても、
それを処理できないようであれば、止めた方がいいです。
士業の業務は、その人がやるから成果が変わる、というのが特徴でもあるので、
流れ作業にはできないと考えています。
だれがやっても結果が同じような業務は面白くありませんし。
そして、人が多くなれば、できない人も増えるのは当然ですね。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
異議申立後の医療照会(交通事故・自賠責保険)
医療照会に関しては、各医療機関によって対応が違います。
自賠責保険の後遺障害等級申請、
特に異議申立申請後は、
ご依頼者が本件事故によって通院したすべての医療機関(接骨院除く)に、
自賠責側から医療照会が入ります。
この医療照会文書について、
各医療機関での作成後、自賠責側に返送する前に、
ご依頼者とともに弊所で記載内容を確認させてもらうことが多いです。
しかし、医療機関によっては、患者本人でさえ、この閲覧や確認を拒否されることがあります。
医療機関ごとに方針・対応がありますので、
ここで、医師法などを駆使して「なんで閲覧できないのか?」と強気に出るようなことは弊所ではしません。
医師法や法律を持ち出しても、ダメな時はダメ。
こうなったら、医療機関は梃子でも動きません。
この場合は、医療機関や主治医先生を信頼して結果を待つしかありません。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
開示手続(交通事故・自賠責保険)
とある開示手続が完了しました。
さて、
どんな書類、
どんな情報が取得できて、
それを踏まえてどう動くか。
真価が問われます。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
やめること、捨てることはない(交通事故・自賠責保険)
交通事故による自賠責保険の後遺障害等級申請・異議申立申請をする場合は、
(1)通院をやめないこと、
(2)取得した書類は捨てないこと、
もポイントです。
通院をやめないこと
通院については、自分の中で後遺障害等級の結果に納得がいくまでは、継続すべきです。
付け加えると、後遺障害等級申請や異議申立申請後、
主治医先生に追加で診断書作成の協力をしてもらうこともありますので、
後遺障害等級結果に納得行くまでは通院の継続は必須です。
症状固定後、後遺障害診断書受領後、
ぱったりと通院をやめてしまうのは、あまりにも淡白な対応です。
人としては定期的に挨拶したり、顔を見せたりする人の方が、愛着が湧くというものです。
後遺障害等級認定を勝ち取るには、心理戦も重要です。
捨ててはいけない書類
書類ついては、診断書はもちろんのこと、
(A)領収書
(B)相手方損保会社から送られてきた書類
などなど、捨てる書類は一つもないと思ってください。
こういった書類の管理も弊所でいたします。
取得した書類を弊所に送って、
書類管理を依頼するだけでも、弊所に依頼する利点はあります。
交通事故による自賠責保険上の後遺障害申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでご相談・ご依頼ください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。