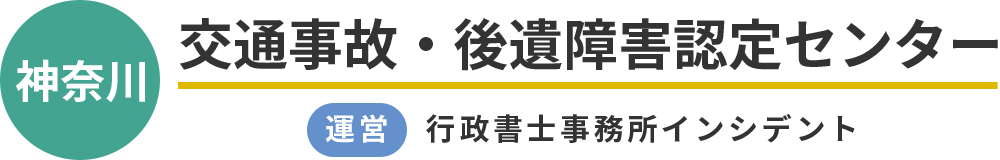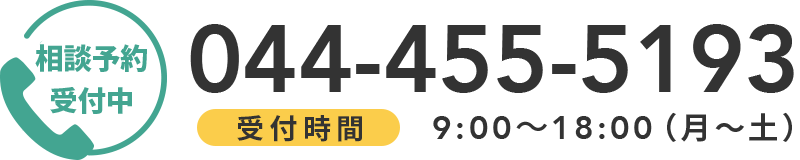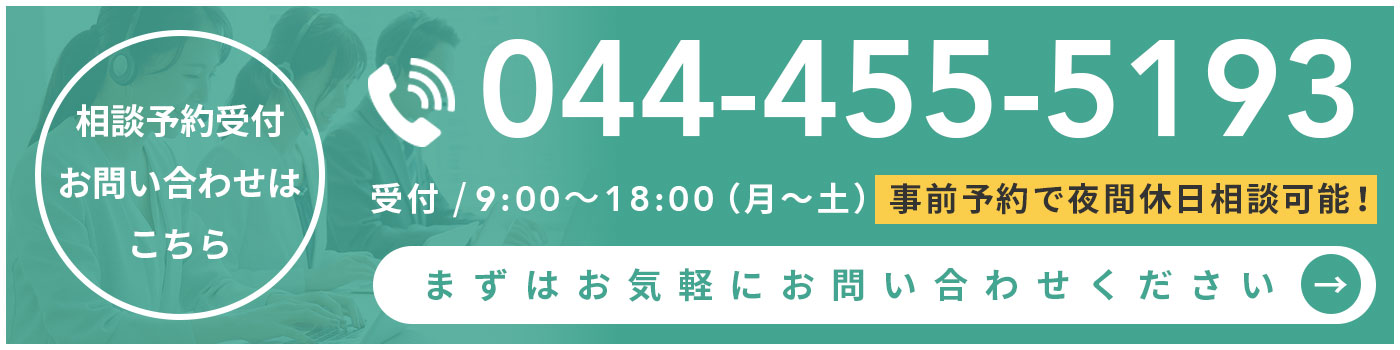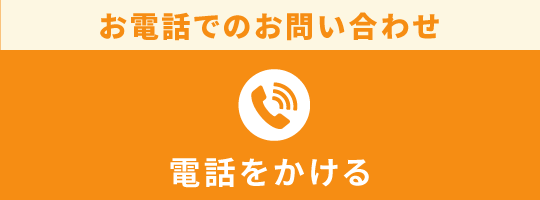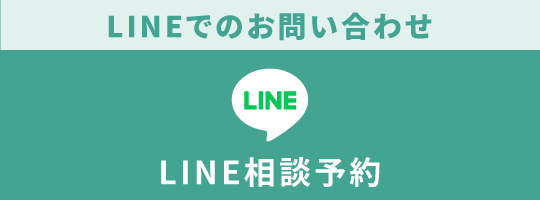このページの目次
通院の中断は不利になる
交通事故による怪我の治療は、1ヶ月(=30日)程度の中断があると、
治療費の打ち切りの対象になる可能性が高まります。
この1ヶ月以上の中断は、
(A)仕事や家事、学業で忙しくてやむを得ず通院できなかった、という事情もあれば、
(B)主治医先生の指示で、「次回は1ヶ月後に診せてください」という指示による場合もあります。
(B)の具体例としては、鎖骨骨折の実例を思い出します。
鎖骨骨折は、交通事故後、手術対応になりプレート固定術が行われることがあります。
その後、骨癒合が確認でき次第、プレート除去手術となるのですが、
プレート除去後は、医師の指示で「月1回程度の診察」に切り替わることがあり、
その間、リハビリの指示もありませんので、
医師の指示にそのまま従うと、1ヶ月の通院の空白ができるケースがあります。
これは、治療費打ち切りの対象にもなりますし、
後遺障害審査上も通院の空白ができるということは連続性・一貫性が途切れることになりますので、
非常によくない状況となります。
連続性と一貫性を好む自賠責保険
交通事故による怪我の治療を6ヶ月超、相手損保会社に補償をいただけた実例をみますと、
いずれも、週2~3回の通院ペースを維持しているのが特徴です。
これは、医療機関・整形外科から相手損保会社に毎月届く診断書や診療報酬明細書から、
・通院のペース
・治療の内容
を確認し、被害者の、「怪我を回復させようとする努力がある」と判断していただいているおかげでもあります。
一方、通院のペースにばらつきがあったり、通院のペースが落ちてくると、
「治ってきた」という判断を診断書等の書面で判断され、
治療費の打ち切りの対象者にされるのであろうと察します。
症状固定後も通院は継続すべき
そして、弊所に異議申立のご相談者に多いのが、
症状固定を迎えた日に、通院をすべて止めてしまっていることです。
通院のペースは週1回や2週間に1回としてもよいので、
後遺障害等級申請の結果を確認し、被害者自身が納得するまでは、通院は継続することが最善です。
初回の後遺障害等級申請で、認定となるのは一番ですが、
初回は「非該当」である可能性もあります。
非該当の結果に対して、異議申立申請を試みる際、
「症状固定後も通院を継続していること」が、とても重要な新たな医学的所見になります。
症状固定後も通院を継続していることにより、
症状が重篤で、その症状に苦しめられている、ということをアピールすることができます。
6ヶ月超の、週3回の通院は本当に疲れることと思いますが、
症状固定を迎えて終わりではありません。
むしろ、新しいスタートになります。
交通事故賠償問題に真剣に取り組むとなると、かなりの根性が必要になります。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。